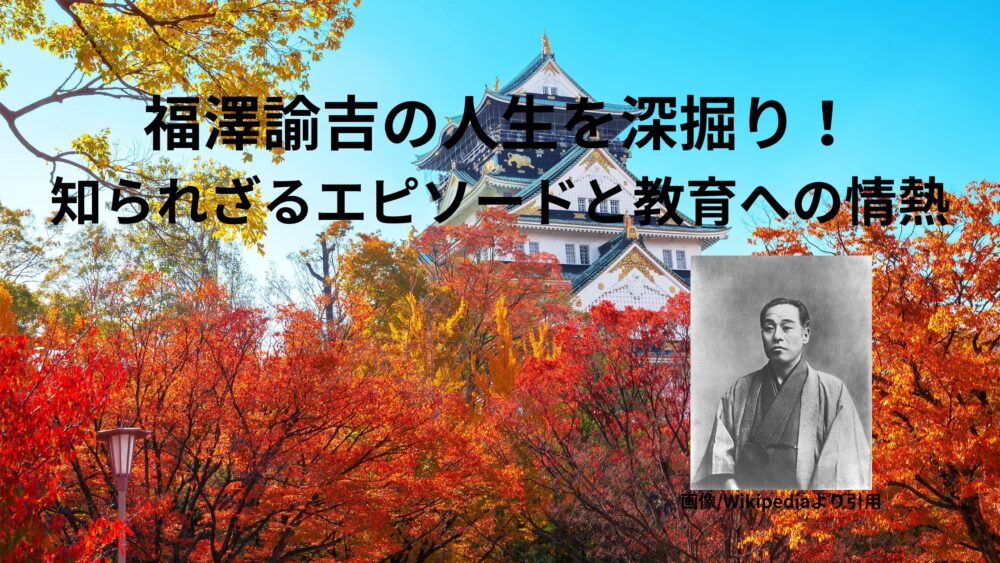福澤諭吉の有名な話の一つとして「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」という言葉があります。これは、彼の著書『学問のすゝめ』の冒頭部分で記された一節で、日本の教育史において非常に有名です。
この言葉は、「人は生まれながらにして平等である」という近代的な平等主義を示しており、封建社会の身分制度を否定する思想を表しています。ただし、福澤はその後に「学問を修めた者が社会で成功する」という主張を続けており、単なる平等主義に留まらない、学問の重要性を強調した現実的な視点が含まれています。
この言葉と思想は、日本の近代化と個人の自由の礎を築いた福澤諭吉の象徴として広く知られています。
留学費用を自力で捻出
幕末期の海外渡航の背景
- 福澤諭吉は幕末から明治初頭にかけて、合計3度 海外に渡っています。
- 1860年(万延元年):遣米使節団(咸臨丸乗船)に通訳として随行
- 1862年(文久2年):遣欧使節団に参加
- 1867年(慶応3年):パリ万国博覧会へ向かう幕府使節団に随行
- これらはいずれも幕府の公式派遣だったため、船賃や最低限の渡航費などは基本的に幕府や藩の予算から出ています。その一方で、個人的に追加で学びたいことがあったり、書籍を購入したり、より自由に滞在期間を延ばしたりする場合には自分の資金を使ったとも伝えられています。
留学費用「自力捻出」とはどういう意味か
- 著作・翻訳活動による収益
- 福澤は早くから蘭学・英学を修め、訳書や学習書の執筆をしていました。1860年代以降には『西洋事情』などの著書がベストセラーとなり、当時としては珍しく執筆で大きな収益を得ることができました。
- こうした収益は、慶應義塾の前身となる私塾の運営資金にも充てられましたが、自身が海外で書籍を購入したり、滞在中に必要となる個人的な経費を補うためにも使われたといわれています。
- 家塾や教育活動での収入
- 福澤は幕府や藩からの給金(蘭学者や通訳としての役職手当)だけでなく、江戸の築地鉄砲洲や芝新銭座などで開いていた塾(のちの慶應義塾)での授業料収入も得ていました。
- 私塾の運営には費用がかかる一方で、優秀な講義と評判を得れば多くの門人が集まり、ある程度の収益も見込める環境でした。その収益を留学に際しての個人的な支出に回した可能性もあります。
- 藩からの十分な支援がなかった可能性
- 福澤が生まれた中津藩は比較的財政が豊かではなかったこと、また幕末の動乱期であったこともあり、充分な支援が期待しにくい状況がありました。
- よって、自身で資金を確保しないと十分な研究・学習ができないという事情があったのではないかと推測されています。
- 海外渡航中の追加費用
- 幕府の公費が出るのは使節としての“最低限の活動費”に限られることが多く、現地での追加の学習や書籍・器具の購入、あるいは自由行動のための滞在延長などをしたい場合には、自己資金が必要でした。
- 福澤は海外の進んだ技術や書物を貪欲に吸収しようとしたため、渡航先で多くの書籍や文具・器具を買い込んだといわれ、その費用は執筆収入や塾収益などによって補ったとされています。
実際の資金フローに関する史料的な難しさ
- 幕末から明治初期にかけては政治・社会情勢も混乱しており、「個人資金」と「公的資金」の線引きが明確でなかったり、記録が十分に残されていなかったりする場合も多くあります。
- 福澤自身が後年に書いた『福翁自伝』などからは、当時の体験談や心境がうかがえますが、すべてが詳細に記されているわけではありません。
- そのため、「留学費用を自力で捻出した」というエピソードがある一方で、「公式使節団としての費用は幕府が負担していた」という事実もあるので、「どこまでが公費で、どこからが私費なのか」 は単純に区切りづらいのが実情です。
まとめ
- 公式使節としての海外渡航費用は基本的に幕府や藩の公費から支出されていた。
- 一方で、現地での追加の学習や書籍購入、自由行動にかかる費用については、福澤が執筆・翻訳・教育活動などによって得た収入を投じていたとみられる。
- 当時としては珍しく、自身の著作や学塾経営で大きな収益を得られた点が、福澤が「自力で留学(の追加費用)を捻出した」と語られる大きな理由になっている。
参考になる史料・書籍
- 『福翁自伝』(福澤諭吉 著)
- 『学問のすゝめ』(福澤諭吉 著)
- 『西洋事情』(福澤諭吉 著)
- 各種、慶應義塾史関連の研究書や論文
補足
「留学」という言葉を現代的に捉えると「私費留学」をイメージしがちですが、福澤諭吉の場合は公務による「使節団随行」という形での海外経験が中心でした。そのうえで、個人的に学んだ部分や購入した書籍・資料の費用を自己資金で補った、というのが実態に近いと考えられます。
■マーケニスタ|Webマーケティング・動画制作・デザイン・DX・AI関連のオンラインサロン型の学習サービス
16カテゴリ600レッスン以上のコンテンツがあり、随時更新中。
月1回のオンライン勉強会、月1回のオンラインのワーク会など充実のサポート。

家族への厳格な教育方針
特別扱いの禁止
- 福澤は「子供だから」「自分の子供だから」といった理由で特別扱いすることを強く嫌いました。
- 慶應義塾(当時は慶應義塾の前身の私塾を含む)に子供が入塾する際も、他の塾生と同様に扱うよう徹底しており、試験の結果によっては容赦なく落とすことも辞さない姿勢でした。
- これは福澤自身が「人は生まれながらに平等である」と考えていたこととも関連し、「身分や家柄だけに頼るのではなく、自らの力で道を切り開け」という思想を家庭内でも実践していた例といえます。
身をもって示す倹約と勤勉
- 福澤は幼少期からの苦労や、蘭学・英学を身につけるために切磋琢磨した自身の経験もあって、「贅沢は身を滅ぼす」「勤勉こそが人を成長させる」という信念を強く抱いていました。
- 子供たちに対しても、無駄遣いや贅沢を厳しく戒め、倹約や勤勉を推奨しました。
- 当時は既にベストセラー作家・教育者として相応の経済力があったにもかかわらず、華美な生活を避け、家族にも質素な暮らしをするよう求めています。
家庭教育の一環としての「自立」と「責任」
- 福澤は「子供はいつか社会に出て、自立しなければならない」という考えのもと、幼少期から「自分で考え、自分の責任で行動すること」を叩き込みました。
- たとえば、何か失敗をしたときや問題を起こしたときは、子供自身に解決策を考えさせることを重視し、いたずらに親が先回りして助けたりはしなかったといわれています。
- これによって、子供たちは自然と独立心を養い、将来どのような立場になっても「親の七光り」に頼らない気概を持つことを期待していたのです。
遊興や飲酒への制限
- 福澤は慶應義塾の学生にも禁酒令を出したことがあるほど、無駄な遊興や浪費に対して厳しい態度を取りました。
- 家庭内でも同様であり、子供たちが学業を疎かにして酒や遊びに興じることは認めないという方針でした。
- ただしこれは「文化的な楽しみ」や「健全な交友関係」まで否定するものではなく、あくまでも「勉学を中心に据えるべき年齢に、度の過ぎた遊びは不要」と考えていたようです。
成功や名誉よりも「人格と実力」を重視
- 福澤は子供たちに「成功しろ」「大きな仕事を成し遂げろ」というよりは、「人として正しくあり、かつ社会に役立つ実力を養う」ことを強く求めました。
- その背景には、日本の近代化において欧米に学んだ「個人の尊厳」「実学の価値」という考え方がありました。家柄や名声だけではなく、実力で評価されるべきだと説いたのです。
- これは、「人間性の確立や知識・技能の習得こそが大事であって、地位や名誉はあくまで結果に過ぎない」という福澤の一貫した信念でもありました。
家族との関係性
- 以上のように厳格な父親であった一方、福澤は子供たちの自立や個性を尊重し、大切に思う気持ちも強く持っていました。
- 『福翁自伝』などを読むと、ユーモアを交えながら子供たちへ説教をする場面があったり、彼らの前で欧米での体験談を語って興味を引き出したりするエピソードが散見されます。
- 家庭内ではスキンシップや会話を通じて、「勉強しなさい」だけではなく、「学問とはこういう面白さがあるんだ」ということを伝えていたとされ、厳しいだけではない「愛情ある教育者」の側面も窺えます。
まとめ
- 福澤諭吉の家庭教育は、慶應義塾での教育理念と同様に「自立」「平等」「実力主義」「勤勉」を基盤にしていました。
- 「子供でも特別扱いしない」「贅沢や無駄を許さない」「自分の頭で考えさせ、行動させる」 といった厳格さが特徴的です。
- 同時に、厳しさの裏には「子供たちが将来、社会に出て困らないようにしたい」「自分の足で立ち、生き抜いていけるように」という深い愛情もあり、当時としても先進的な教育観だったといえます。
こうしたエピソードからは、福澤諭吉が単に「近代教育の父」という立場だけでなく、「父親としての厳しさと愛情」を両立させようとしていた人間像が浮かび上がってきます。
「脱亜論」は元々非公開の意図だった
「脱亜論」が“非公開”あるいは“私的”だったとされる理由
- 署名がなかったため、真意や著者が曖昧だった
- 『時事新報』の社説は必ずしも署名付きではなく、編集主幹や寄稿者による“匿名”の論説が多く載っていました。
- 「脱亜論」もその一つで、明確に「福澤諭吉が書いた」とクレジットされていたわけではありません。
- したがって当時、「福澤本人の公式見解なのか、それとも社内の誰かの寄稿なのか」は曖昧なままだったと推測されます。
- 福澤が生前に公に再録・再出版しなかった
- 福澤は自著をしばしば書籍化・改訂したり、講演録をまとめたりしていましたが、「脱亜論」を自らの著作集(『福澤全集』や諸論集)に入れることはありませんでした。
- そのため、「あの記事は一過性のものであって、意図的に再録しなかったのではないか」「本人が大っぴらに主張として残すほどのものではなかったのではないか」といった見方も生まれています。
- 公的には“刺激が強すぎる”内容だった可能性
- 1880年代の国際情勢や当時のアジア情勢(清国や朝鮮半島との関係をめぐる問題)は非常に複雑でした。
- 「脱亜論」が示すような、近隣諸国に対して厳しい姿勢を取ることは、政治的に波紋を広げるリスクがあります。
- こうした背景から、福澤が当初から「論説として載せるのはよいが、後で大々的に拡散されるのは望んでいなかったのではないか」という推測をする研究者もいます。
- 死後に初めて大きく注目された
- 「脱亜論」は新聞の一社説にすぎず、福澤本人の膨大な執筆活動の中でも、ごく短文の小論でした。
- そのため、福澤没後に日清戦争(1894~1895)や日露戦争(1904~1905)が起こり、日本の対アジア政策が大きく変化していく流れの中で、後世になってから「先見の明を示した文章」として注目された側面があります。
- こうした経緯もあり、「福澤自身が生前にこれを強く打ち出したわけではない」「後世に再発見された」という印象が、“もともと非公開(あるいは公に残すつもりのない文章)だった”と語られる一因となっています。
実際には“完全な非公開”ではなく、当時も新聞に掲載されていた
- 実際のところ、「脱亜論」は『時事新報』という全国的に読まれた新聞に掲載されており、当時としては決して“誰の目にも触れない私的な文章”ではありません。
- ただし、匿名社説であるために「福澤自身の手になるもの」と読者がすぐに認識できたかどうかは不明瞭です。
- いずれにせよ、一度新聞に載った以上、まったくの“非公開”ということはあり得ません。むしろ「大々的に署名をして自分の主張だと示す形ではなかった」というのが事実に近いでしょう。
なぜ「もともと非公開の意図だった」という説が広がったのか
- 福澤の「脱亜論」不採録
- 先述のとおり、福澤は著作集に「脱亜論」を収録しませんでした。
- そのため後世の人々は「福澤自身があまり大っぴらにしたくなかったのでは?」と推測するようになりました。
- 内容の過激さ・時流との関係
- 「アジア近隣諸国を見放し、日本だけが欧米を手本として進むべき」という論調は、当時のアジア主義や伝統的な儒教的価値観からすればかなり急進的・過激に映ります。
- 後の植民地支配や侵略的な対アジア政策を想起させる言説でもあるため、現代の感覚ではさらにセンシティブな問題になります。
- こうした“政治的に微妙”な論調ゆえに、福澤自身も後になって強くは主張しなかったのかもしれません。
- 「福翁自伝」など他の文献との整合
- 福澤は自伝や他の著作で、教育・独立自尊・平等主義などを強く説いており、「脱亜論」のように他国への露骨な批判を全面に押し出す文章はあまり多くありません。
- したがって、福澤の思想全体をみると「脱亜論」が例外的に見える部分もあり、“あえて大きく取り上げなかったのでは”という見方も生まれています。
結論:本当に「非公開の意図」だったかは不確か
- 史実として確かなのは、「脱亜論」は1885年に『時事新報』へ掲載され、当時の読者にとっては“公開された”文章であったということです。
- 「福澤が後生までこの文章を広めたかったのかどうか」「なぜ著作集に収録しなかったのか」といった点については、福澤自身が明確に理由を残していないため、研究者の間でも様々な解釈があります。
- 一方で、「福澤諭吉=脱亜論」のみで評価すると、福澤の思想全体を正確に理解できなくなる恐れもあるため、近年の研究では福澤の多面的な言動・著作の中の一つとして位置づけるという見方が主流になりつつあります。
参考になる文献や研究
- 『時事新報』明治18年3月16日付社説(「脱亜論」原文)
- 福澤諭吉『福翁自伝』
- 岩波文庫『福澤諭吉選集』ほか(ただし「脱亜論」が収録されていない版もある)
- 近代日本思想史学・ジャーナリズム史における研究論文(「脱亜論」再検討に関するもの)
まとめ
- 「脱亜論」は当時の新聞に公表された文章であるため、厳密には“非公開”ではありませんでした。
- しかしながら、匿名の社説であったこと、福澤の公式著作集に収められなかったこと、そして内容が政治的に過激な面を持つことなどから、
- 「福澤諭吉が積極的に広めたい主張とは考えていなかったのではないか」
- 「後に再録されるつもりで書かれたものではないのでは」
という説やイメージが広がり、「もともと非公開にする意図があった」と語られがちになったのが実情です。
結論としては、「はっきりと意図を示した本人の証言がない以上、『元々非公開にするつもりだった』というのは推測の域を出ない」 ものの、
- 福澤が生涯を通じて大々的に「脱亜論」を宣伝・引用しなかった
- 公式な著作集に掲載されなかった
といった事実から、“福澤本人にとっても扱いが微妙な論説だったのではないか”と推測されている、というのが実態です。
■Nakasho|40代からの新しい美髪体験。イオントリートメント「アイマイナス」
見た目年齢を上げてしまう、ツヤの無いパサついた髪。
イオントリートメント【アイマイナス】は、本来の自分のツヤ髪に戻すウォーターミストです。

健康への強い意識
「身体の健康」と「知的活動」の不可分性
- 福澤諭吉は幼少期から体が特別に弱かったというわけではありませんが、若いころから「体力・健康が学問や仕事の基礎になる」という考えを強く持っていました。
- これは、欧米を視察した経験や海外の書物(医学書や衛生学関連の文献など)を通じて、西洋の健康観や医療制度に触れたことが大きく影響したと考えられています。
- 精神(知力)と身体は切り離せないという認識は、当時の日本ではまだ一般的ではなく、先進的な見解でした。
毎日の習慣:運動・散歩・早寝早起き
- 日常的な散歩や軽い運動
- 福澤は朝や夕方に散歩をする習慣を身につけていたと言われています。とりわけ江戸や明治期の東京においては、交通手段が今ほど発達していないこともあり、よく徒歩で移動していたようです。
- これにより適度に汗をかき、体を動かすことが健康維持にとって大切だと考えていました。
- 早寝早起き
- 西洋での生活を見聞したこともあってか、「夜更かしは身体に悪い」「朝早く起きるほうが仕事も勉強もはかどる」という考えを実践していました。
- 当時の慶應義塾でも、学生に対してなるべく早寝早起きをするよう指導していたという記録があります。
食事・飲酒に対する姿勢:節度・倹約
- 暴飲暴食を戒める
- 福澤は自らが創設した慶應義塾の学生にも禁酒令を出したことがあるほど、過度の飲酒や贅沢な食事を好まず、節度を守るように指導していました。
- これは単に道徳的・経済的な理由だけでなく、健康のためにも良くないという認識からきています。
- 質素でバランスの良い食事
- 幕末~明治初期、日本の食文化はまだ欧米の栄養学的な知見と完全には接合していなかった時代ですが、福澤はできる限り栄養バランスを考えつつ、贅沢や偏食を避けるようにしていたと伝えられています。
- 「豪華な食事=良いこと」というよりは、「体を壊さない、持続可能な食事」という考え方で、子供たちや周囲の塾生にも同様の姿勢を促していました。
衛生・医療への関心
- 西洋医学の導入
- 福澤は若い頃、緒方洪庵の適塾(大阪)に学んで蘭学を修めており、当時最先端の西洋医学・自然科学の基礎知識に触れています。
- 幕末~明治期にかけて、日本ではまだ和漢医学(漢方)と西洋医学が併存する時代でしたが、福澤は病気の原因解明や衛生管理における西洋医学の優位性を早くから理解していました。
- 清潔さの重視
- 近代的な衛生概念(うがいや手洗い、入浴、下水整備など)は欧米から少しずつ導入されましたが、福澤はこれらを積極的に取り入れるよう説いています。
- とくに江戸時代には公衆衛生の概念があまり確立しておらず、感染症の流行を防ぐ上で重要な「手洗い」「建物の換気」なども、欧米視察で学んだ知識を生かしていたと考えられています。
学生・家族への指導
- 福澤は厳格な教育方針を家族にも学生にも徹底しましたが、健康に関しても同様でした。
- 暴飲暴食や夜更かしの禁止
- 慶應義塾の塾生が酒に溺れたり、遊興にふけって夜更かしするようなことがあれば、厳しく戒めています。
- 適度な運動の推奨
- 学生の身体を鍛え、学問をするにも健康第一と説いていました。明治以降、学校教育に体育(体操)が取り入れられていく流れとも合致します。
- 日常生活のリズムを整える
- 福澤家の子供たちにも「生活習慣を乱さないこと」を口酸っぱく言い聞かせ、家族自身も模範を示そうとしていたようです。
- 暴飲暴食や夜更かしの禁止
晩年までの健康維持と死去の様子
- 福澤は明治34年(1901年)に満66歳(数え年67歳)で亡くなりましたが、当時としては比較的長命といえる年齢でした。
- 晩年は脳溢血(脳卒中)の症状などがあり、一時体調を崩していましたが、それでも健康への注意を怠らず、できる限り規則正しい生活を続けようとしていたと伝えられています。
- 最期は体調悪化に伴う合併症が原因とされていますが、それまで長年にわたり教育活動や執筆に情熱を注ぎ続けられたのも、若い頃からの健康管理の賜物だと見る研究者もいます。
まとめ
- 福澤諭吉は、「健康あってこその学問・仕事」という近代的な健康観・衛生観を持ち、日本の近代化期において先進的な“健康第一”の考えを広める先駆者の一人でした。
- 具体的には、
- 早寝早起きや散歩による適度な運動
- 過度な飲酒・贅沢な食事の自制
- 衛生・医療(西洋医学)の導入と実践
- 学生や家族にも徹底した生活習慣の指導
といった行動を通じ、健康を大切にする生活スタイルを貫いていました。
- こうした姿勢は、現代の“ヘルスケア”や“セルフマネジメント”に通じる考え方としても評価され、福澤の先進性や行動力を示すエピソードとして知られています。
まとめ
福澤諭吉は「身体の健康あってこそ学問や仕事が成り立つ」という考えを強く持ち、日常的な散歩や早寝早起きを習慣とし、暴飲暴食を戒めるなど、当時としては先進的な「健康第一」の生活を実践していました。西洋で学んだ医学・衛生の概念を取り入れ、学生や家族にも規則正しい生活と衛生管理を勧めるなど、厳格ながらも愛情のこもった指導を行い、近代日本において「健康管理」と「学問」を結びつける先駆的な思想を示した人物といえます。
■必ずトレーナーがつくフィットネスクラブ「Forzaフィットネススタジオ」
パーソナルトレーナーが複数のお客様を同時に指導するセミパーソナルトレーニング方式を採用したフィットネスクラブです。

■HR CAREER AGENT|人材業界特化の転職エージェントへの転職相談
人材業界と転職市場の両方を熟知したプロフェッショナルが、ベンチャー企業から大手企業まで幅広く優良企業をご紹介しています!

■JAPAN&GLOBAL eSIM|海外旅行・出張なら手軽で便利なeSIM
このeSIMを利用することで、物理的なSIMカードを差し替えることなく、スマートフォンなどの対応デバイスでデータ通信が可能になります。旅行者やビジネスユーザーにとって便利で、手軽に日本国内外でインターネット接続をすることができます。