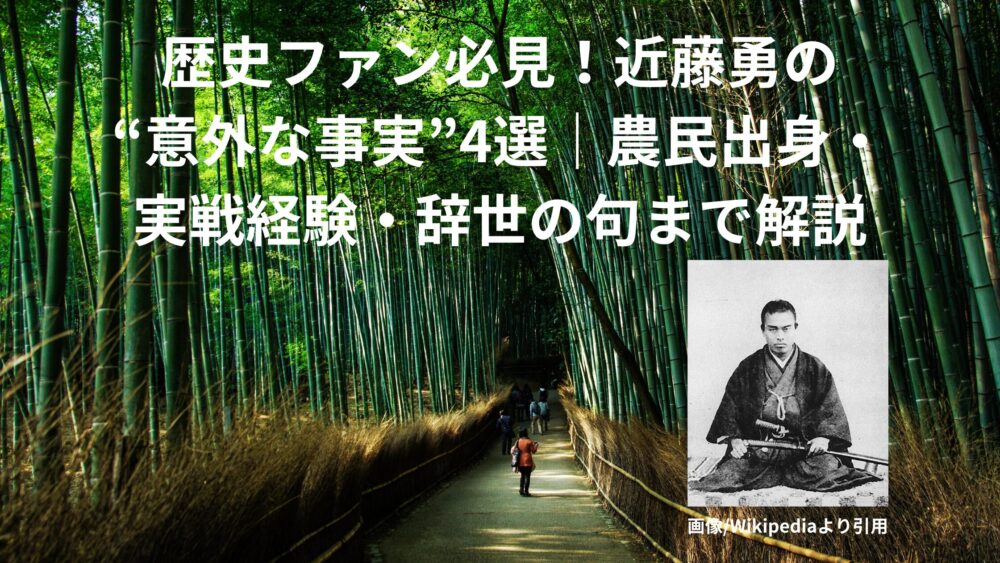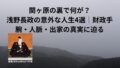✅ 池田屋事件での新選組の大活躍
1864年(元治元年)6月、京都・池田屋にて発生した「池田屋事件」は、近藤勇と新選組の名を一躍全国に知らしめた代表的な出来事です。
この日、新選組は尊王攘夷派の志士たちが京都で大規模な放火・騒乱を企てているという情報を掴み、分隊して捜索を開始。近藤勇はわずか十数名を率いて、池田屋で密会していた長州・土佐・肥後などの志士たちを急襲します。
この戦いは大混戦となりましたが、近藤は自ら刀を振るいながら指揮をとり、見事に十数人の志士を斬り伏せて捕縛。この結果、幕府内外で新選組の評価が急上昇し、「京都守護職の剣」としての地位を確立します。
この事件は、近藤勇=勇猛果敢な剣士、忠義の士というイメージを決定づけたエピソードとして、歴史ファンに広く知られています。
実は「武士」ではなく“農民出身”だった?
新選組の局長として名を馳せた近藤勇(こんどう いさみ)は、その堂々たる風格と剣の腕から「生まれながらの武士」と思われがちです。しかし実は、彼の出自は武士ではなく、多摩地方の農民でした。
近藤勇の本名は「宮川勝五郎(みやがわ かつごろう)」。1834年、現在の東京都調布市にあたる多摩郡の農家に生まれました。彼の家系は名主でも郷士でもなく、れっきとした農業従事者の家でした。
そんな勝五郎少年が武士を目指すきっかけとなったのが、天然理心流(てんねんりしんりゅう)という剣術道場への入門です。剣術修行に励み、その実力を認められていきます。そして、ついには道場の師範である近藤周助(こんどう しゅうすけ)の養子となり、「近藤勇」と名を改めました。
この“養子入り”が、彼にとっての大きな転機でした。武士階級ではなかったものの、武士の名を持つ家に入ったことで名実ともに「剣術家=武士」としての道を歩み出すことになったのです。
後年、幕末の京都で新選組を率いたとき、彼はあくまで“武士”として振る舞い、上下関係を重んじる厳格な規律を隊士たちに課しました。それは裏返せば、農民出身という自分のルーツを乗り越えようとする強い覚悟の表れでもあったのかもしれません。
このように、近藤勇の“出世譚”は、剣と覚悟で運命を切り開いた一人の青年の、知られざる苦闘の物語でもあるのです。
■馬刺しの極み|初回限定!極み馬刺し3種お試しセット
「馬刺しの極み」では、熊本産の厳選された本格馬刺しをお届けしています。

「実戦経験」は少なかった?新選組局長の意外な一面
近藤勇といえば、新選組を率いた剣の達人として知られ、数々の死闘を繰り広げた“戦う局長”というイメージが強い人物です。しかし実際には、彼自身の大規模な戦闘経験はそれほど多くなかったという見方もあります。
新選組の主な任務は、幕末の京都での市中警備と尊王攘夷派の取り締まりでした。その活動の多くは、斬り合いというよりも内偵や逮捕、時には密偵としての動きが中心で、刀を抜く機会は思われているほど多くありません。
たしかに有名な「池田屋事件」では、近藤自ら先頭に立ち奮戦し、尊攘派志士たちを捕縛するという大功績を挙げています。しかしそれ以外の大規模な戦闘となると、彼が実際に刀を手にして戦った記録は限られているのです。
さらに、戊辰戦争が始まってからは、新政府軍との戦争が本格化する中で近藤は指揮官としての役割に徹するようになり、自ら剣を振るう場面は減少します。むしろ政治的交渉や、部隊の再編・命令系統の整備といった“裏方の戦い”が中心となっていきます。
つまり近藤勇は、戦闘の最前線よりも、組織運営と統率力で力を発揮したリーダーだったのです。剣の腕だけでなく、人心掌握術や戦略眼を持ち合わせた「現場指揮型のカリスマ」として評価すべき存在とも言えるでしょう。
幕臣になれたのは「一時的なもの」だった?
近藤勇は、長年の念願だった「武士として正式に幕府に仕える」夢を、1867年にようやく叶えます。尊王攘夷派の取り締まりや池田屋事件での功績が評価され、徳川慶喜から正式に“幕臣”に取り立てられたのです。
これは、農民出身であった彼にとってまさに「武士の頂点」に立った瞬間でした。名実ともに武士階級の一員となり、身分的にも“新選組局長”から“徳川家家臣”へと格上げされます。
しかし、その栄光はわずか数ヶ月で失われることになります。
1867年10月、大政奉還が行われ、徳川幕府は事実上の終焉を迎えました。翌1868年には鳥羽伏見の戦いを皮切りに戊辰戦争が勃発。幕府の官僚組織も崩壊し、近藤が得た「幕臣」という地位は、歴史の大転換の中で無意味なものとなってしまったのです。
さらに皮肉なことに、近藤は旧幕軍として新政府軍に追われる立場となり、敗戦を経て捕らえられ、最期は斬首されてしまいます。つまり、彼が“幕臣”として名乗れた期間は、ごく短く、実質的には「名ばかりの出世」で終わってしまったとも言えるのです。
とはいえ、彼がその短い間にも「武士としての誇り」を胸に行動し、最後まで旧幕府に忠義を尽くしたことは、今なお多くの人の心を打ちます。夢を掴んだ直後に時代に翻弄された男――それが、近藤勇のもう一つの顔です。
■駅市 薩摩川内|鹿児島県の特産品
黒豚や薩摩揚げ、安納芋を使用したスイーツなど盛りだくさん。
ここでしか手に入らない鹿児島県の特産品をお取り寄せ。

最期の言葉は「武士らしさ」そのものだった?
新選組局長・近藤勇は、幕末の動乱の中で旧幕府軍として戦い続け、1868年、板橋刑場(現在の東京都北区)で斬首されてその生涯を終えました。その際に彼が遺したとされる辞世の句は、今なお多くの人の胸を打つものです。
「望みをば 捨て果ててしも みちのくの しのぶもぢずり 誰かたづねん」
この句は、「もはや望みは捨てた。東北(会津)へと向かった我が身を、誰が訪ねてくれるだろうか」という意味合いを持っています。敗者として忘れ去られるかもしれない自分を静かに受け入れつつ、忠義を尽くした道の重さをにじませる一句です。
また、処刑前には自ら「腹を召す覚悟はある」と申し出たとされ、斬首ではなく切腹を望んだという説もあります。新政府側はこれを許さず、斬首刑を選びましたが、近藤の姿勢からは最後まで“武士であり続けること”にこだわった気概が見て取れます。
農民出身というハンディを乗り越え、「剣と忠義」で生きた近藤勇。最期の時まで武士としての誇りを手放さずにいたその姿は、倒れながらも武士道を貫いた人物として、後世の人々の心に深く刻まれています。
まとめ
新選組局長として名を馳せた近藤勇は、一見すると「生まれながらの武士」のように思われがちですが、実際は農民出身という異色の経歴の持ち主でした。その出自を乗り越え、剣一本で身を立て、幕府から正式に幕臣として認められるまでに至った彼の生き様は、まさに“成り上がりの武士道”そのものです。
しかし、その華々しい評価の裏には、意外にも多くの実戦を経験していなかった一面や、出世の喜びがわずか数ヶ月で崩れ去るという無常な現実がありました。幕末という激動の時代の中で、近藤勇は時代の波に翻弄されながらも、最期の辞世の句まで「武士らしさ」を貫いた男でした。
彼の人生を改めてたどると、ただの剣豪や忠臣ではなく、自らの意思と信念で武士としての道を歩みきった一人の人間としての魅力が見えてきます。表舞台だけでなく、その背景にある“知られざる素顔”こそが、近藤勇の真の人物像を語る鍵となるのです。
■melike_(ミライク)|ワンランク上のスタンダードユニセックスウェア
創業76年、ニット専門として、長年の歴史でつちかった数多くの開発技術を洗練させ、時代にフィットした素材やシルエット、着用感を提供しつづけています。

■PRIMESHOP.JP通販サイト|健康的で美味しいイタリアの食材・調味料などの商品
primeshop.jpというイタリア食と健康ライフスタイルに関するブログで紹介した食材を中心として、
高級イタリアンレストランで使用される食材を紹介しています。

■マーケニスタ|Webマーケティング・動画制作・デザイン・DX・AI関連のオンラインサロン型の学習サービス
16カテゴリ600レッスン以上のコンテンツがあり、随時更新中。
月1回のオンライン勉強会、月1回のオンラインのワーク会など充実のサポート。

■グリーンラビット
可愛らしいうさぎやネコのデザインが施されたアパレルコレクション。メンズ・レディースともに楽しめる、シンプルながらも遊び心のあるデザインが魅力です。カジュアルなTシャツやスウェットから、上品なシャツやジャケットまで幅広く展開。