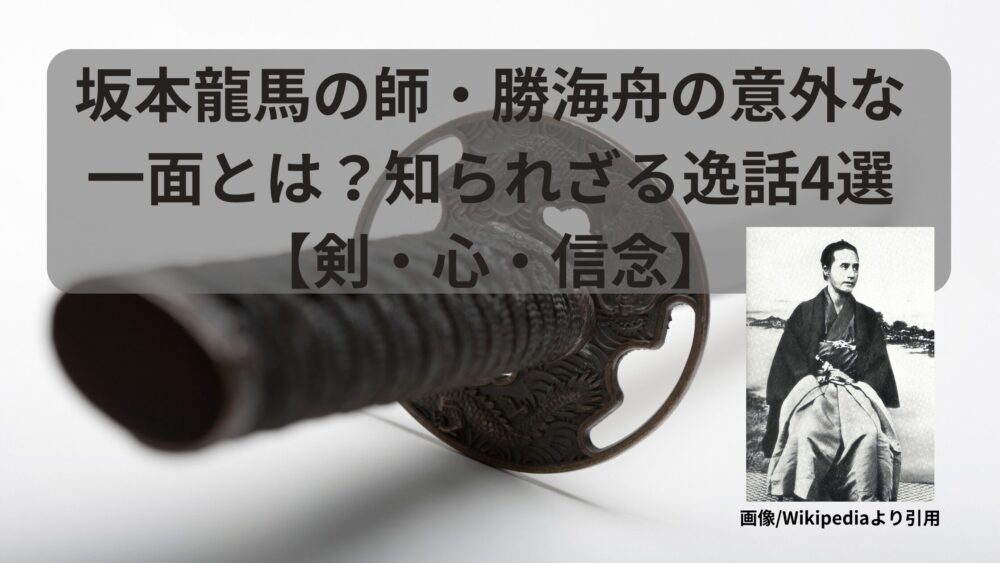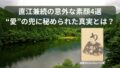【江戸無血開城を実現した英雄】
1868年、明治維新の激動期。
新政府軍(西郷隆盛率いる薩摩軍)が江戸に迫る中、もし戦争になれば江戸の町は火の海になり、百万人の市民が巻き添えになる可能性がありました。
この危機的状況で、勝海舟は旧幕府側の代表として西郷隆盛と直接交渉。互いの信頼と未来への覚悟により、ついに「戦わずして江戸城を開け渡す=無血開城」を実現させたのです。
これは世界史的にもまれな、首都の平和的移譲であり、日本の近代化を進める上で極めて重要な分岐点となりました。
剣術の達人だった勝海舟が「剣では世は変わらぬ」と語った理由とは?
■ 若き日の勝海舟は「剣客」だった
勝海舟(幼名:麟太郎)は、若い頃から剣術に長けており、「神陰流(しんかげりゅう)」の免許皆伝を受けるほどの実力を持っていました。幕臣の中でも腕前は評判で、実際に剣の道を志していた時期もありました。
彼は江戸の剣術道場に通い、鍛錬を積む中で数多くの実戦経験を積んだとされ、文武両道の幕臣として将来を期待されていたのです。
■ しかし、勝は「剣を極めても社会は変わらない」と気づく
剣術の稽古に没頭する日々の中、勝はある時、ふとこう考えます。
「いくら剣が強くても、それだけでは民を救えない。時代を動かすのは“知”と“対話”なのだ」
実際、幕末の動乱の中で、剣による争いではなく、外交・交渉・国際感覚が重要になることを、彼は若いうちから痛感していました。ペリー来航、欧米列強の脅威、国内の政争……剣で斬ってどうにかなる時代ではないと悟ったのです。
■ 「剣では世は変わらぬ」発言の背景
勝がこの言葉を口にしたのは、主に坂本龍馬や西郷隆盛など、多くの志士たちと接する中で、若い者たちが“武力革命”に傾倒している風潮を憂えたときとされています。
彼は坂本龍馬にも「これからの日本は、刀じゃない。話し合いで未来を切り開くべきだ」と教え、海軍・外交・国際貿易など“新しい時代の武器”を伝えようとしました。
■ 実践で証明された信念
この信念は、のちに実際に形になります。
そう、「江戸無血開城」。
西郷隆盛との話し合いによって、首都・江戸は一滴の血も流さず明け渡されました。もし彼が剣に固執していたら、江戸は火の海となっていたでしょう。
「剣を捨て、言葉と信念で時代を導く」
それが勝海舟の“剣より強い道”だったのです。
■ この言葉の現代的意義
この発言は、ただの理想論ではなく、武士の時代から市民の時代へと移行する象徴でもあります。
力よりも対話、武力よりも交渉。勝海舟は、日本が近代国家として生まれ変わるための「精神的な橋渡し役」を果たした人物だったといえるでしょう。
■博多もつ鍋おおやま|もつ鍋おおやま公式通販サイトの商品
もつ鍋の本場福岡県で売上NO.1(帝国データバンク調べ)のもつ鍋店です。
飲食店を全国に20店舗展開し、年間食数約100万食(延べ約1200万食)を販売しています。

江戸無血開城の立役者でありながら、当初は“幕府の強硬派”だった?
■ 江戸無血開城=勝海舟の代表的功績
1868年(慶応4年)、戊辰戦争の最中、明治新政府軍(主に薩摩・長州連合)は旧幕府軍を駆逐しながら東進し、ついに江戸城を包囲します。このとき、江戸市中は100万人を超える人口を抱え、ひとたび戦火が及べば多大な犠牲と焼失が避けられない状況でした。
その中で流血を避けて城を明け渡す「江戸無血開城」を成し遂げたのが、旧幕府側代表の勝海舟と、新政府軍代表の西郷隆盛でした。
■ だが、最初から「和平路線」ではなかった?
意外なことに、勝海舟はこの交渉に至る前、幕府内では「徹底抗戦」を主張していた一人だったという記録が残っています。
当時、鳥羽伏見の戦いに敗れた旧幕府軍に対し、江戸では「挙兵してでも巻き返すべきだ」「戦って名誉を守るべきだ」との声が高まり、勝もまた一時はその流れに乗っていました。彼は、「武士の本分は一戦にあり」とする価値観を一度は受け入れていたのです。
■ 転機となったのは“現実的判断”
しかし、次第に状況を冷静に分析するようになります。
武力で抗えば江戸の街が火の海になる――それは避けねばならない。
とくに、勝の心を動かしたのは、市民や非戦闘員が巻き添えになる悲劇でした。軍事的にはまだ戦える余地があると思われていましたが、「勝っても意味がない、負ければ地獄、どちらにせよ江戸が滅びる」と判断したのです。
■ 西郷隆盛との信頼と交渉
勝は西郷隆盛に使者を送り、直接交渉の場を設けます。
慶応4年3月13日(1868年4月11日)、薩摩藩屋敷で行われた会談で、両者は約3時間にわたり徹底的に議論。そこで勝は「市民を守るためなら、私の首などいくらでも差し出す」とまで語り、戦争回避を説得しました。
結果、江戸は戦火を免れ、穏やかに政権が移行する歴史的快挙が達成されました。
■ 「強硬派」から「和平派」へ――勝の柔軟さと胆力
このエピソードが示すのは、勝海舟の本質が“頑固者”ではなく、現実を見て判断を変える柔軟性と覚悟を持ったリーダーだったという点です。
自分の意見に固執せず、「何が最善か」を冷静に見極め、場合によっては180度方針を変える――これは、時代の転換点において極めて重要な資質でした。
■ 歴史が評価した「決断力」
後世、多くの歴史家がこの江戸無血開城を「日本が内戦状態に陥らず、明治維新を比較的平和裏に成し遂げた最大の理由」と評価します。
そして、その裏にあった勝海舟の「強硬派から和平交渉人への転身」は、まさに“時代に必要とされた変化”を象徴する出来事といえるでしょう。
幕臣ながら“坂本龍馬の師”となったことに悩みもあった?
■ 勝海舟と坂本龍馬――有名な師弟関係
幕末の英雄・坂本龍馬には多くの影響を与えた人物がいますが、最も象徴的な師といえば勝海舟です。
龍馬が勝の門を叩いたのは文久2年(1862年)頃。ちょうど勝が海軍伝習所の設立を進め、近代的な日本の防衛と外交の道を模索していた時期でした。当初、土佐藩の脱藩浪士だった龍馬は幕府にとって「政治的に危うい存在」。しかし、勝はその志と行動力を高く評価し、正式な弟子として受け入れ、薫陶を与えました。
■ しかし「幕臣としての葛藤」も大きかった
勝は幕府の高官(軍艦奉行など)であり、徳川家に忠義を尽くす立場にありました。そのため、脱藩浪士=幕府の秩序を乱す存在を身近に置くこと自体、周囲から強い反発を受けました。
とくに、龍馬が徐々に“倒幕思想”へ傾いていく中で、勝自身も心の中で葛藤を抱えます。
「自分が育てた龍馬が、やがて幕府を倒すことに加担するのではないか――」
「それでも見捨てることはできない」
このジレンマの中で、勝は政治的リスクを承知の上で龍馬を見守り続けます。
■ 勝の覚悟:「時代の人間を育てる」
勝はのちに周囲にこう語っています。
「俺は幕臣として龍馬を育てたんじゃない。
あいつは、時代を動かす“人間”だから育てたのさ。」
この言葉には、個人の立場や組織の論理を超えた、時代を見据える勝の先見性と覚悟がにじんでいます。
坂本龍馬の自由な発想、大局を見据える行動力、そして後の「船中八策」などに通じる政治観は、勝の影響なくしては語れません。たとえ師弟が思想的にすれ違うことがあっても、勝は最後までその成長を誇りに思っていました。
■ 勝が流した“後悔の涙”
慶応3年(1867年)、坂本龍馬が暗殺されたという報が届いたとき、勝海舟は人目もはばからず、ぽろぽろと涙をこぼしたと伝えられています。
「惜しい男を亡くした……」
「あれほどの人間は、もう出てこん」
自らの進む道に疑問を抱きながらも、時代の流れを受け入れた勝。
そして、信じて育てた龍馬が命を懸けて成し遂げた維新の一歩。
このエピソードは、勝が「幕府の人間」でありながら「時代を超える師」となった稀有な存在であることを象徴しています。
■Winenot?|ワインセット
フランス産の本格ワイン100ml×5本(赤3本、白2本)セット、ギフトボックス付き

晩年は“仏像”に囲まれた隠居生活を送っていた?
■ 明治維新後、政治の表舞台から退く
明治維新後、幕臣であった勝海舟は新政府からも一定の信任を受け、明治政府に出仕します。参議や海軍卿などを務めるものの、明治10年代に入ると政界の中枢から距離を置き、次第に表舞台から退いていきます。
勝の考えは、「政治は若い者に任せる。自分は口を挟まぬ」というもので、あくまで時代の流れを尊重し、自らは静かに去る姿勢を取りました。
■ 自宅に“数百体”の仏像を並べた生活
晩年、東京・赤坂氷川町に住んでいた勝の邸宅は、まるで仏像博物館のようだったといわれています。
居間や書斎、廊下にまで大小さまざまな仏像が置かれ、観音菩薩、地蔵菩薩、阿弥陀如来など、多様な像がずらりと並んでいたそうです。
仏像はただの美術品ではなく、勝にとって心の支え、静けさの象徴、精神的な寄る辺でした。
■ なぜ仏像に惹かれたのか?
剣と政治の世界を生き抜いた勝が、なぜ仏教や仏像に傾倒したのか――その背景には、激動の人生を振り返る中での“内面の安らぎ”への渇望があったと考えられます。
明治という新時代を見届け、盟友や弟子たちの死、かつての幕府の崩壊――その一つひとつが勝にとっては“失う経験”でした。
やがて彼は、仏像を見つめながら思索にふける日々を過ごすようになります。
「この世は移ろい。静けさの中にしか真実はない」
という心境に至ったとも伝えられています。
■ 晩年の語録にも“仏教的観念”が表れる
勝海舟は、晩年に多くの語録や回顧談を残していますが、その中にはしばしば「無」「空」「因果」といった仏教用語や観念が見られます。
たとえば——
「世の中は、何もかも“思いどおりにはならぬ”が、それでよい」
「物事に執着せず、ただ静かに身をまかせるのがよい」
これはまさに、仏教の根本思想である「諸行無常」「無執着」の体現ともいえるものです。
■ 最後まで“俗”と“聖”を併せ持つ人物だった
勝海舟の晩年の姿は、単なる隠遁ではありません。
彼は仏像に囲まれていても、訪ねてくる若者とはよく語らい、時に皮肉を交えた辛口コメントを投げるなど、俗世の感覚もしっかり残していた人物でした。
つまり、勝は「聖人君子」になろうとしたのではなく、“人間としての円熟”を仏像と共に追い求めたのです。
■ 総じて:静かなる幕引き
剣、外交、政治――波乱の時代を駆け抜けた勝海舟が、最終的に求めたのは、人としての心の静けさ。
その象徴が、赤坂の邸宅に並んだ仏像たちだったのです。
まとめ
幕末から明治へ――激動の時代を生き抜いた勝海舟は、単なる“幕臣”や“政治家”では語り尽くせない多面的な人物でした。
若き日は剣術に秀でながらも「剣では世は変わらぬ」と悟り、知と対話の力で江戸無血開城という歴史的快挙を成し遂げました。
一方で、坂本龍馬という“敵方”の若者を育てることに悩みながらも、「時代の人間を育てる」という信念を貫きました。
そして晩年は、仏像に囲まれた静かな生活の中で、動乱の時代を振り返りながら「無常」や「平穏」を見つめていたのです。
戦うことよりも、守ること。
変わらぬ信念と、時代に応じた柔軟さ――
勝海舟の生き方には、現代に通じるリーダー像と、人間的な深みが詰まっています。
■本格出張バーベキューCRIB|【競合優位性あり】手ぶらで楽しめる出張BBQの予約
本格出張バーベキューは手ぶらで楽しめるBBQの一括請負サービスです。本格的なBBQグリルから職人が仕込んだ食材まで全て弊社がご用意してBBQ会場にご用意いたしますので、お客様は本格的なBBQを手ぶらで楽しんでいただけます。

■CHIBASAKE.com|日本酒・焼酎・リキュール・生酒を取り扱う地酒専門
千葉県の日本酒・焼酎・リキュール・生酒を取り扱う地酒専門サイト。28の酒造から厳選された美味しい日本酒を取り扱っています。

■ハチイチ商店|\メディア掲載多数/岩手県のご当地グルメ「瓶ドン」の商品
「瓶に詰まった宮古の恵みを、ほかほかご飯にまるごとかけて」をコンセプトとした「瓶ドン」。
三陸 宮古の魅力的な海鮮をかわいらしい牛乳瓶に詰め、さまざまな海鮮が美しい層になっています。

■グリーンラビット
可愛らしいうさぎやネコのデザインが施されたアパレルコレクション。メンズ・レディースともに楽しめる、シンプルながらも遊び心のあるデザインが魅力です。カジュアルなTシャツやスウェットから、上品なシャツやジャケットまで幅広く展開。