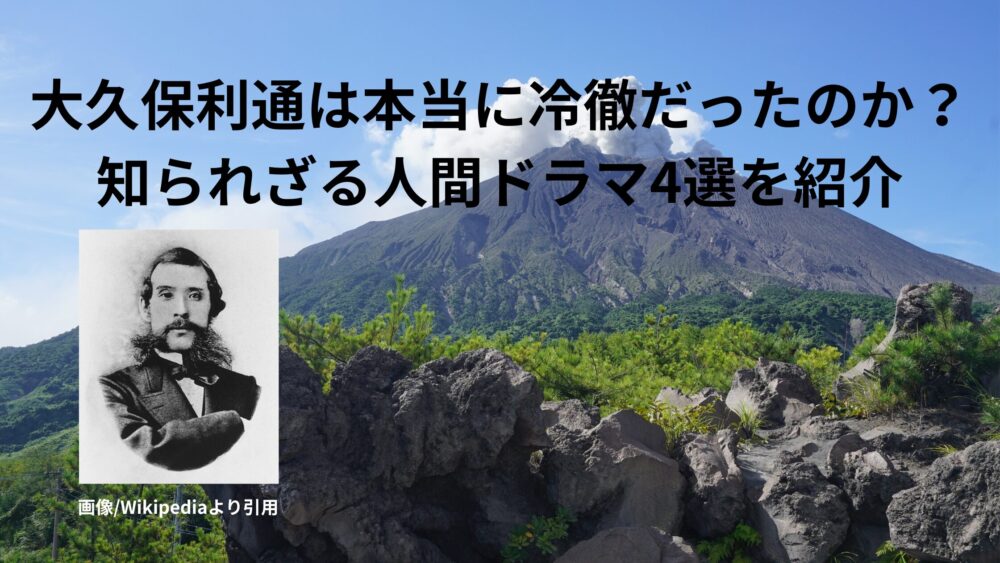✅【有名な話】「紀尾井坂の変」で暗殺された明治の最高実力者
1878年(明治11年)、大久保利通は紀尾井坂(現在の東京都千代田区)で不平士族によって暗殺されました。
これは「紀尾井坂の変」と呼ばれ、当時の日本に大きな衝撃を与えました。
大久保は、明治政府の中枢にあり、廃藩置県や地租改正など近代国家の礎を築いた人物ですが、その急進的な改革によって、士族層から激しい反感を買っていました。
彼の死により、政府内には一時的に動揺が走りましたが、皮肉にもこの暗殺によって明治国家はより中央集権化を進めていく契機となりました。
実は「暗殺」を何度も警戒し、私生活も徹底していた?
――明治の最高実力者が抱えていた“恐怖”と“用心”
大久保利通は、明治政府の中心人物として、廃藩置県・徴兵令・地租改正・学制導入など、数々の近代化政策を強力に推し進めました。しかしその反動で、特に士族層や攘夷派からは“裏切り者”とみなされ、強い憎悪の対象となっていきます。
◆ 常に「暗殺リスク」を想定していた
大久保自身もその危機感を強く持っており、政務が終わって帰宅する時間や移動経路は絶対に固定せず、日によってルートや時間を細かく変えていたといわれています。また、東京と京都・鹿児島を行き来する際には複数の宿泊先を利用し、「前もって予定を明かすことはなかった」と記録にも残っています。
さらに、自宅には護衛を常駐させるだけでなく、家族にも来客の素性確認を徹底させるなど、家庭内のセキュリティ意識も非常に高かったと伝えられています。
◆ “私邸”も軍事拠点さながら?
大久保の東京・永田町の私邸は、当時としては異例の堅牢な造りで、玄関には鉄製の扉が設けられ、外部からの視線を遮る高い塀も設けられていたといいます。まるで軍事施設のような造りは、大久保の警戒心の強さを物語っています。
また、玄関脇には常に番兵が立ち、深夜であっても来訪者があれば必ず本人確認と要件の伝達を義務付けていました。こうした「異常なほどの警戒ぶり」は、近隣住民の間でも有名だったそうです。
◆ 皮肉にも、暗殺された「その日」だけ油断していた?
しかし、その慎重な男にも“隙”が生まれてしまいます。1878年5月14日――紀尾井坂で襲撃された当日、なぜか警護の供を連れず、一人で馬車に乗って登庁していたのです。理由については諸説ありますが、「政府内の緊張緩和」や「いつも通り警護が手薄だった」などが語られています。
その油断が命取りとなり、6人の不平士族に馬車を襲撃され、首・肩・胸を斬られ即死。享年47。
日本近代国家をつくりあげた巨星の死は、日本中に衝撃を与えました。
🔍まとめ
大久保利通は冷静な合理主義者であると同時に、常に暗殺の恐怖と向き合いながら生きていた政治家でした。
その徹底した自己管理ぶりは、命を賭けて近代国家を築いた覚悟の証だったといえるでしょう。
■ハチイチ商店|\メディア掲載多数/岩手県のご当地グルメ「瓶ドン」
「瓶に詰まった宮古の恵みを、ほかほかご飯にまるごとかけて」をコンセプトとした「瓶ドン」。
三陸 宮古の魅力的な海鮮をかわいらしい牛乳瓶に詰め、さまざまな海鮮が美しい層になっています。

若い頃は“幕府寄り”だった?思想の転機とは
――実は討幕派ではなかった大久保利通の原点と変化
「維新の三傑」の一人として知られる大久保利通ですが、彼が最初から“倒幕”の思想を持っていたわけではありません。若い頃の彼はむしろ“幕府存続派”に近く、穏健な政治改革を志していた保守的な人物だったのです。
◆ 父・利世の影響と薩摩藩内の立場
大久保は1827年、薩摩藩(現在の鹿児島県)に生まれました。父・利世(としよ)は島津久光の側近として仕えており、大久保もその縁から藩政の中枢へと早くから関わっていきます。
当時の薩摩藩は、幕府に対して敵対するよりも、「公武合体(=幕府と朝廷の協調)」を模索する中道的な立場でした。大久保もこの流れに従い、幕府と朝廷が連携して改革を進めるべきという考えに共鳴していました。
◆ 幕政改革に期待していた時期があった
文久2年(1862年)には、藩主・島津久光が「文久の改革」を掲げて上京した際、大久保はその随行メンバーとして京都入りします。これは、幕政改革を幕府に促すための平和的な政治活動であり、大久保自身もこのときはまだ「幕府が変われば日本も変われる」と信じていた節があります。
事実、この時期の書簡には、過激な攘夷志士たちを批判的に見ていたような記述も残されています。
◆ 転機となったのは「八月十八日の政変」と「禁門の変」
大久保の思想が大きく変わるのは、1863年の「八月十八日の政変」および1864年の「禁門の変」です。
尊王攘夷派が公武合体派に排除される過程や、長州藩が朝廷を巻き込んだ武力衝突を起こしたことにより、平和的な改革では国の行方が危ういと大久保は痛感。
さらに、幕府がこうした政変を有効に収拾できず、内外の混乱を招いたことで、「この政権に未来は託せない」と決定的に判断したといわれています。
◆ 「現実主義者」としての判断
倒幕に傾いた大久保は、坂本龍馬らの仲介によって薩長同盟を実現させ、討幕への布石を打ちます。
このように、彼の思想の変化は感情や激情によるものではなく、「現実を直視し、国家のために必要な選択をした結果」であったことがわかります。
🔍まとめ
大久保利通は、生まれながらの倒幕主義者ではありませんでした。
むしろ、最初は幕府の改革を信じようとしていた理性派。
しかし混迷の政局と時代の転換点を冷静に見極め、現実主義に徹して討幕を選んだ――それが彼の政治的な“進化”だったのです。
親友・西郷隆盛との絶縁、その背後にあった「密約」
――盟友はなぜ決裂したのか?その裏に潜む政治的駆け引き
明治維新の立役者であり、「維新の双璧」とも称される大久保利通と西郷隆盛。
ともに薩摩藩出身であり、若い頃から苦楽を共にし、幕末には討幕の中核を担った二人ですが、明治新政府成立後、彼らの関係は急速に悪化し、ついには「絶縁」とまで言われるほどの決裂を迎えます。
その原因として知られるのが、「征韓論(せいかんろん)」をめぐる対立です。
しかし、表面に現れる思想の違いだけではなく、実はその背後には「密約」や「政治的取引」が存在していたとされるのです。
◆ 表向きの対立:「征韓論」をめぐる衝突
1873年、明治政府内で朝鮮への使節派遣(のちの征韓論)が議題にのぼります。
西郷は、朝鮮に自ら使節として赴き、誠意をもって国交を開き、必要であれば戦争も辞さないという考えを示しました。
一方、大久保はこれに真っ向から反対。
彼は「国内の近代化こそ最優先。いま戦争すれば国家が崩れる」として、朝鮮との衝突を回避すべきだと主張しました。
この意見の対立により、政府内は分裂し、最終的に西郷を含む参議6名が辞職。
以後、西郷は鹿児島に戻り、大久保との間には深い溝ができることになります。
◆ 背後にあった「密約」とは?
実はこの政争の裏で、大久保が征韓論を潰すために仕組んだ「密約」または「政略」が存在していたとも言われています。
■ 木戸孝允・岩倉具視との連携
征韓論争のさなか、大久保は政敵排除のために岩倉具視・木戸孝允らと密かに連携し、西郷ら参議派の辞職を既定路線として演出していたという説があります。
つまり、「西郷らを一度政府から排除し、自分が主導権を握る」という政治的な仕掛けだったというわけです。
■ 「西郷を引退させるための計画」説
また、別の説では、「西郷を朝鮮に行かせれば、政権内の影響力を自然と弱められる」と見た大久保が、当初から使節派遣に消極的なふりをしながら、結果的に西郷を政府から遠ざけるシナリオを描いていたとも。
いずれにしても、征韓論そのものよりも、権力闘争としての色彩が強かったというのが、近年の研究者の間でも有力視される視点です。
◆ 決裂の果てに生まれた“西南戦争”
1877年、鹿児島で挙兵した西郷は、「西南戦争」を起こし、最期は城山で自決します。
その直前、大久保は「彼に戦争をさせてはならない」と何度も説得を試みましたが、西郷の決意は変わりませんでした。
この戦争の後、大久保は「西郷を死なせてしまった」と深い罪の意識を抱えていたとされ、日記や手紙には“西郷を悪人と思ったことは一度もない”といった記述も見られます。
🔍まとめ
大久保と西郷の決裂は、単なる意見の違いではなく、明治国家の方向性をめぐる本質的な争いであり、
その裏には、大久保の政治的計算や“密約”的な動きも絡んでいた可能性が高いのです。
親友を政治的に排除した男――その選択は、冷徹さと国家への情熱が交錯した「苦渋の決断」だったのかもしれません。
■Fishlle!(フィシュル)|未利用魚サブスクの新規購入
業界初・未利用魚を使用したミールパックのサブスク「Fishlle!(以下フィシュル)」のプロモーションです。

最期の懐には「家族への手紙」が隠されていた?
――暗殺された大久保利通が遺した、もう一つの“遺言”
1878年(明治11年)5月14日、東京・紀尾井坂。
明治政府の中枢、大久保利通は、不平士族6人によって馬車の中で襲撃され、無残にも命を落としました。
刃による傷は首・肩・胸部など複数に及び、即死。47歳でした。
この襲撃は「紀尾井坂の変」として知られていますが、実はこの事件には、もう一つの“静かなドラマ”があったと伝えられています。
◆ 遺体の懐から見つかったものは、政治文書ではなく「家族宛の手紙」
事件後、大久保の遺体が確認された際、懐に大切にしまわれていたのは、国家の極秘書類でも重要政策の草案でもなく、“家族への私信”だったという記録が残っています。
手紙の詳細な文面は現存していませんが、内容は「子どもたちや妻への思い、今後の家計についての指示、そしてもしものときに備えての心づもり」が書かれていたと伝えられています。
彼が、自身の死を予感していたような文調だったとも言われています。
◆ 暗殺を覚悟していた男の“静かな覚悟”
大久保は日頃から暗殺のリスクを強く意識していたことで知られ、登庁の経路や滞在先を頻繁に変え、警備も怠りませんでした。
それでも、あの日に限って護衛をつけず、単身で登庁したのです。
その不可解な行動は、未だに議論が絶えませんが、なかには「覚悟の上だったのではないか」という説もあります。
そして、家族への手紙を肌身離さず持っていたことが、その“死の予感”を裏づけているのではないかと考えられているのです。
◆ 政治家としての顔ではなく、「父・夫」としての姿
国の行く末を第一に考え、政敵さえも排除し、冷徹な実務家と評されることの多い大久保利通ですが、
この一通の手紙が、彼に「人間としての温かさ」や「家庭を思う父の一面」があったことを静かに語っています。
特に、彼の家族宛の手紙には、「自分がいなくなっても、恐れず誇りを持って生きてほしい」という思いが込められていたと伝えられ、
その内容に涙した使用人もいたという逸話が残っています。
🔍まとめ
紀尾井坂での突然の死。そのとき大久保が遺したのは、国家の方針書ではなく、家族への静かな遺言でした。
それは、激動の時代を生き抜いた政治家の、最後にして最も人間的な一面を映し出す“もう一つの遺産”だったのです。
まとめ
明治維新の立役者として、日本の近代化を強力に推し進めた大久保利通。
冷静な政策家、冷徹な実務家として知られる彼の裏には、常に命の危険と隣り合わせの緊張感、親友との苦渋の別れ、そして家族を思う優しさがありました。
若き日は幕府存続を模索し、時代の流れを読み倒幕へと転じ、
かつての盟友・西郷隆盛と訣別してでも国家の安定を優先し、
ついには警戒していた暗殺を避けられぬまま、懐に家族への手紙を残してこの世を去った——。
その一生は、理想と現実、信念と計算、人間味と政治力が交錯する、まさに近代日本の縮図ともいえる存在です。
偉業の陰にあった「もうひとつの顔」を知ることで、私たちは歴史上の人物を、より深く“人間”として理解できるのかもしれません。
■スエヒロ家|創業1935年イベリコ豚・黒毛和牛専門店
創業1935年老舗肉屋がお届けする、最高級のお肉、イベリコ豚・国産黒毛和牛を伝統の包丁さばきと、目利きで美味しい笑顔と共にお届けします。

■はかた寿賀や|博多明太子
多明太子の食べ比べができる詰め合わせセットを販売しています。
また、明太子からすみや糸島燻製など、お酒に合う明太子おつまみもございます。

■SONOKO|8週間ダイエット献立お試し1週間献立
創業者鈴木その子が「太るメカニズム」に着目した「食べるだけ」ダイエットです。
代謝を良くすることで太らない体を作り、油分をできる限り減らし、無添加にこだわることで、
「炭水化物」・「3食+間食+夜食」をとりながら「健康的に」痩せることを実現しております。

■グリーンラビット
可愛らしいうさぎやネコのデザインが施されたアパレルコレクション。メンズ・レディースともに楽しめる、シンプルながらも遊び心のあるデザインが魅力です。カジュアルなTシャツやスウェットから、上品なシャツやジャケットまで幅広く展開。