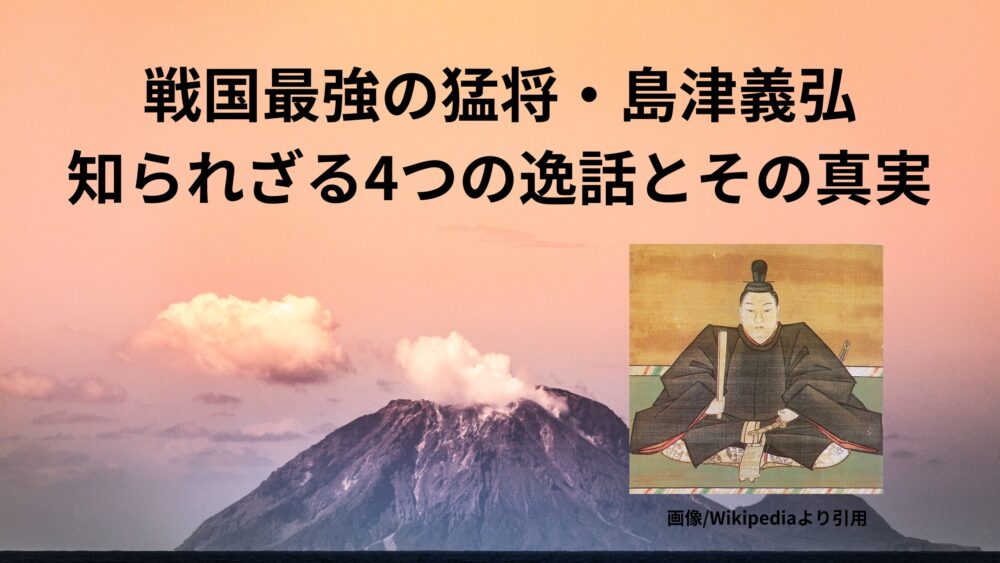島津義弘の有名な話として最も知られているのは、やはり 「島津の退き口」 です。
島津の退き口(関ヶ原の戦い・1600年)
1600年の関ヶ原の戦いで、西軍に属していた島津軍は戦局の悪化により孤立し、四方を東軍に囲まれます。通常なら降伏か全滅しか選択肢がない状況でしたが、義弘は降伏を拒否し、逆に敵陣の中央を突き破るという奇策に出ます。
殿(しんがり)役の部隊が東軍に突撃して注意を引き、その間に義弘本隊が一直線に突破する――この命がけの撤退戦が「島津の退き口」です。
この作戦により義弘は薩摩への帰還に成功し、以後「不屈の武将」として名声を高めました。
関ヶ原の戦い「島津の退き口」
戦いの背景
1600年9月15日、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が関ヶ原で激突。
薩摩の島津義弘は西軍に属していたものの、三成の戦略や政治手腕を信用しておらず、開戦当初は動かず、南の松尾山付近で様子をうかがっていました。
義弘の島津軍は約1,500〜1,800名と小規模。一方、東軍は数万規模で圧倒的な兵力差がありました。
西軍崩壊と孤立
午前中、西軍の小早川秀秋が東軍に寝返ると、戦況は一気に東軍有利に傾きます。
周囲の西軍諸将も次々と敗走し、義弘の島津軍は敵中に孤立。普通なら降伏か全滅しかない場面でした。
しかし義弘は、「降伏すれば薩摩の名折れ」と判断し、唯一残された手段――敵中突破による撤退を決意します。
退き口の戦法
義弘は「前進撤退」という異例の作戦を採用しました。
これは、包囲を突破するために、後方ではなく敵の本陣方向へ進むことで道を切り開く戦法です。
- 殿(しんがり)役:義弟・島津豊久が率い、敵に正面突撃して注意を引きつける
- 本隊:義弘を中心に中央突破
- 犠牲覚悟:突破のため、後方部隊はほぼ壊滅を覚悟
この突撃で島津豊久は壮絶な最期を遂げ、他にも多くの精鋭が命を落としました。
生還と伝説化
義弘はこの突破戦で何度も包囲されながらも、奮戦しながら伊勢路を経て薩摩へ帰還。
敵陣中央を突破して生還するという前代未聞の撤退劇は「島津の退き口」として語り継がれ、義弘の武勇と胆力を象徴する出来事となりました。
この戦いは、兵力劣勢でも戦術と決断力次第で活路を開けることを示す、戦国時代屈指の撤退戦の事例として評価されています。
■創業89年・京都の伝統の味を召し上がってみませんか?
さわやかな酸味のあるお味が大変好評いただいており、ごはんのお供にぴったりです。そのままでももちろん、 刻んでいただき、ごはんと混ぜておにぎりや、チャーハン、ちらし寿司に。マヨネーズと混ぜていただくとピン ク色のしば漬けタルタルになります。京つけものニシダやです。
朝鮮出兵で恐れられた「鬼石曼子」
呼び名の由来
「鬼石曼子(グイシーマンヅ)」は、朝鮮半島の人々や明軍の兵士が島津義弘に付けた呼び名です。
- 鬼(鬼):恐ろしく容赦ない武力を象徴
- 石曼子(シーマンヅ):島津の発音が現地訛りで変化したもの
つまり「鬼のように恐ろしい島津」という意味になります。
文禄・慶長の役での活躍
朝鮮出兵(1592〜1598年)で義弘は、わずか数千の兵を率いて出陣。
しかし、彼の軍は戦場で常に最前線に立ち、時には数倍から数十倍の敵軍と交戦しました。
- 狭い地形を利用した待ち伏せ
- 夜襲による混乱作戦
- 撃っては退くヒット&アウェイ戦法
これらを駆使して、敵の大軍を分断・撃破し続けます。
敵軍の恐怖と伝説化
義弘は戦闘中に一切退かず、逆に劣勢の場面でも突撃を選ぶ胆力を見せました。
また、戦意を喪失した敵には深追いせず、民間人への被害も抑えたと伝わります。このため、敵兵の間では「島津と戦えば必ず多くが死ぬが、降伏すれば命は助かる」と噂されるようになりました。
こうした姿は現地兵士に「鬼の島津」として恐れられる一方、武士としての節度も評価され、義弘の名声は敵陣にも広まりました。
後世への影響
この「鬼石曼子」の異名は、日本国内でも戦国武将としての義弘の勇猛さを象徴する言葉となり、後世の軍記物や物語でもしばしば引用されます。
武力と規律を両立させた指揮官像は、彼が単なる好戦的な武将ではなく、戦術家・統率者であったことを物語っています。
実は戦国随一の“温泉好き”だった?
戦国時代、戦場を駆け巡った武将たちは、常に命の危険と疲労にさらされていました。そんな中で、島津義弘はある意味“異色”ともいえる趣味を持っていました。それが「温泉」です。
義弘は薩摩や九州各地の温泉地をこよなく愛し、とりわけ宮崎県の吉田温泉とは深い縁がありました。ここでは湯屋を改修し、湯治場としての機能を整備。さらには温泉を守る神社を建立し、湯守役を配置して管理規則まで定めたといいます。まさに領主自らが“温泉インフラ”を整えた格好です。
しかし義弘にとって温泉は単なる贅沢ではありませんでした。激戦で負傷した兵の治療や、長期戦で疲弊した部隊の体力回復のために、温泉湯治を積極的に活用したのです。兵士の士気維持、健康管理、そして再出陣への備え――温泉は彼にとって軍事戦略の一部でもありました。
その結果、義弘の軍は他の部隊に比べて戦後の回復が早く、特に朝鮮出兵の寒冷な戦地でも凍死者を出さなかったと記録されています。温泉を愛した一人の武将――しかしその愛は、領国経営と軍略にも通じていたのです。
■創業65年超の海鮮問屋が良質なカニ・うなぎをお届け!
楽天ショップオブザイヤー8度受賞、ヤフーショッピング年間ベストストア10度受賞など 数々の表彰を受けている「越前かに問屋ますよね」が 公式サイト限定価格で、モールよりもお得にカニ・うなぎなどの海産物を販売します。
戦場で家臣に“歌”を詠ませて士気を高めた
島津義弘と和歌の素養
島津義弘(1535〜1619)は、戦国屈指の猛将として知られる一方、和歌や連歌にも通じた文化人でした。幼少期から教養を重んじる家風で育ち、古典文学にも触れており、出陣前や戦陣中でも和歌を詠む習慣を持っていたと伝わります。
戦場での歌会
義弘が特徴的だったのは、戦場という極限の状況下でも家臣に歌を詠ませたことです。
- 出陣前夜に士卒を集め、戦いや忠義、郷里への思いを題材に和歌を詠ませる
- 即興の連歌会を開き、緊張と恐怖を和らげる
- 義弘自身も参加し、巧みな歌を披露して場を盛り上げる
この“戦場歌会”は、ただの趣味ではなく、兵士たちの心を落ち着かせ士気を高める心理的効果を狙ったものでした。
士気向上の仕組み
戦場で歌を詠むという行為は、
- 戦いの前に精神を集中させる“儀式”
- 指揮官と兵の距離を縮める交流の場
- 恐怖や不安を共有し、それを芸術として昇華する時間
こうした要素が兵士たちの結束を強め、「自分たちは文化も理解する誇り高き武士集団だ」という自負心を生みました。
後世への影響
この戦場歌会の記録は、薩摩藩の武家文化の一端として後世に伝わり、薩摩の武士たちが武芸と教養の両方を重んじる価値観を持つきっかけにもなりました。義弘はまさに“武と文”を併せ持つ戦国武将だったといえます。
まとめ
島津義弘といえば「島津の退き口」に代表される豪胆な武将という印象が強いですが、その生涯をたどると、単なる猛将像では収まりきらない多彩な人物像が浮かび上がります。関ヶ原の戦いでは前代未聞の敵中突破を成し遂げ、朝鮮出兵では「鬼石曼子」と恐れられるほどの戦術眼と胆力を発揮しました。一方で、温泉を積極的に活用して兵の治療や士気向上を図る実務家としての一面や、戦場で家臣に歌を詠ませて精神を整える文化人としての感性も併せ持っていました。武勇と知略、そして人心掌握の巧みさ――これらが融合してこそ、島津義弘は戦国屈指の名将として歴史に名を刻んだのです。
■楽天グルメ大賞受賞のおせち等、自然派「食」のお取り寄せ
・楽天おせちセットランキング14年連続1位! ・2度目の楽天グルメ大賞を受賞、楽天総合ランキング8年連続1位(デイリーランキング)入賞
楽天グルメ大賞受賞のおせち等、自然派「食」のお取り寄せ【ちこり村本店サイト】■おうちをレストランに変える食ブランド【TastyTable FOOD】
調理は簡単、約10分で完成します。 ソースを解凍して麺と絡めるだけでレストランクオリティーのパスタが出来上がり。
■ボトル型とまったく違う新しい浄水型サーバー
・ボトル交換の必要なし! ・水道水を入れて不純物を97%濾過
■グリーンラビット
可愛らしいうさぎやネコのデザインが施されたアパレルコレクション。メンズ・レディースともに楽しめる、シンプルながらも遊び心のあるデザインが魅力です。カジュアルなTシャツやスウェットから、上品なシャツやジャケットまで幅広く展開。