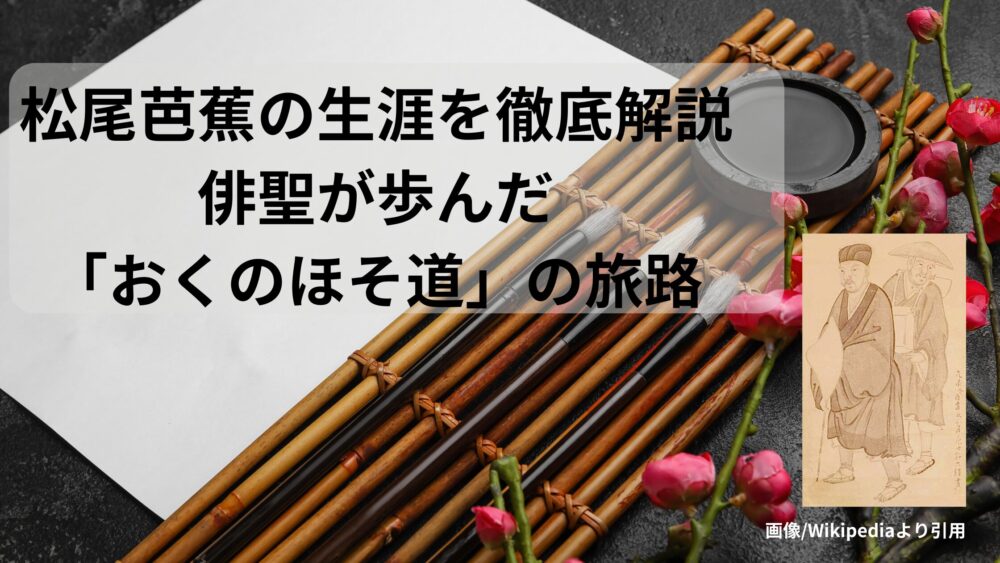松尾芭蕉でもっとも有名なエピソードは、以下の「古池」の一句が生まれた瞬間の話です。旅の途中、ひっそりとした古い池のほとりで耳を澄ませていた芭蕉が、突然「ポチャン」と蛙の飛び込む音を聞き、その場で古池や蛙飛び込む水の音(ふるいけや かわずとびこむ みずのおと)という俳句を即興で詠みました。この一瞬の「間」と音のとらえ方が、後世に「俳聖」と称される所以となり、日本文学史上最も象徴的な一句として語り継がれています。
蛙の葬式を執り行った
背景と時期
貞享3年(1686年)の春、深川の芭蕉庵で開かれた「蛙合」(蛙をテーマにした句合)の席が終わった翌日、芭蕉は門人と別れて一人、近くの小川沿いの道を散策していました。その折、舗道に転がる一匹の死んだ蛙を見つけ、思わず足を止めたといいます 。
葬儀の準備
- 遺体の取り扱い
死骸を強い光の下にさらさぬよう、そっと掌に移し替え、近くの笹の葉を敷いて安置。 - 小石と草で墓標を築く
周囲にあった小石数粒と折れた小枝を用い、手のひらサイズの簡易的な墓標を形づくりました。 - 水振りと清め
帰路で立ち寄った茶店から少量の煎茶を分けてもらい、蛙の遺体にそっと振りかけて浄めを行ったとされます。
慰霊の句と弔辞
傍らにあった和歌用の紙片(歌仙紙)に、芭蕉はこうしたためました(口伝)――
蛙(かわづ)の命(いのち)や露(つゆ)とともに消ゆる寒(かん)の暮れ
(意訳:蛙のいのちも露と同じくはかなく消えゆく、寒い夕暮れ)
その後、静かに一拝し、小さな卒塔婆代わりの枝を墓標に立てかけたと伝わります。
供養の所作
- 線香の代わりに茶筅(ちゃせん)の音
あえて線香を用いず、茶筅を茶碗の中でそっと撹(かく)した時の「シャン」という余韻を、焚香の代わりに聴かせたとも言われます。 - 芭蕉の所感
この一連の所作を終えたのち、芭蕉は門人に向けて「命のはかなさを詠むことは俳諧の本懐に通ず」と語り、しばらく無言で夕闇に沈む小川を見つめたといいます。
※エピソードの真偽について
この「蛙の葬式」逸話は、芭蕉の死後に神格化が進む中で創作された数多くの物語のひとつです。一次史料に直接の記述はなく、具体的な日時や句片も後世の俳諧史家の想像と口伝に依っています。研究のうえでは「芭蕉門下で伝承された逸話」として位置づけられることを留意してください。
■タイムテクノロジー公式ショップ|精密機械や計測機器、試験機器など
精密機械や計測機器、試験機器など中国製品を扱っており、中国メーカーから直接製品を仕入れて販売をしております。

橋の下で夜を明かし寒さをしのいだ
1. 時期と場所
寛文10年(1689年)春、芭蕉は『おくのほそ道』の旅で江戸を発ち、奥州路を北上していました。その道中、雪解けの冷たい風が吹きすさぶ山間部の小川に架かる木橋の下で、宿が取れずに夜を迎えたと伝わります。
2. 野宿に至った理由
当時は街道沿いの宿場もまだ整備途上で、宿の空きもなく、同行の曾良や門人とも別行動となった芭蕉は、やむなく橋の下に避難。小屋のような遮蔽物もない中、深々と冷え込む夜をしのぐしかありませんでした。
3. 寒さをしのぐ工夫
- 蓑と笠の活用
持参していた蓑(みの)と笠(かさ)で体を覆い、橋桁の外気を遮断。 - 草や苔で寝床づくり
橋げた下に生える草や苔を集め、その上に横たわって簡易の野営床としました。 - 余熱を閉じ込める工夫
身体を丸く縮め、蓑の内側に息を吹きかけて温めることで、凍てつく夜露を防いだといいます。
4. 逸話として語られる詠句
この体験の直後、芭蕉は橋の下から見上げた凍てつく川面を前に、短い俳句を詠んだと伝わります。しかし、その句は現行のどの写本や日記にも残っておらず、口伝句として後世にのみ流布しました。
5. 伝承の意義
門人の記録によれば、芭蕉はこの寒さの中で「旅の苦難こそ俳諧の糧(かて)」と語り、過酷な旅路で得た感覚や発見が、その後の深い詩情を育んだとされています。こうした逸話は、俳聖・芭蕉の「苦行と詩の美学」を象徴するものとして語り継がれています。
※注意:
この「橋の下で野宿した」話は、芭蕉の自筆記録には見えず、江戸中期以降の俳諧史家や門人の口伝をまとめた逸話集にのみ登場します。一次史料での裏付けはなく、伝説としてお楽しみください
大名の招待を俳句でやんわり辞退
招待主と背景
江戸中期、地方の有力大名(諸説あり)が蕉庵(芭蕉の隠棲する庵)を訪ね、藩邸での雅宴句会に芭蕉を招聘しようとしました。大名は「蕉風を領内にも取り入れたい」との意図をもっていたと伝わります。
招待状の形式
招聘状は家紋入りの書式で、正装した藩士が蕉庵におもむき、畳の一隅で丁重に差し出したとされます。文面には「老翁の筆力を拝聴し、諸侯の前で披露あらんことを」といった格式高い文言が並んでいました。
芭蕉の思案
招待状を受け取った芭蕉は、一介の旅人としての身分と「山水と詩情を道連れにする」という俳諧の本懐との折り合いを深く考え、格式ある席に身を委ねることに逡巡したといいます。
やんわり辞退の一句
最終的に芭蕉は招待状の裏面に短い発句をしたため返却しました。写本に残る伝承句は次のような趣旨です:
門(かど)開かず 山野(さんや)の風ぞ 招くまま
これには「藩邸の門は開かないが、山野の風がいつでも私を招いてくれる」という含みがあり、庵の外でこそ俳諧があることを穏やかに示しています。
辞退後の顛末
大名は芭蕉の機知に感嘆し、笑顔で許したうえで庵の近くに小規模な句会を再度催しました。しかし芭蕉はあくまで自らの庵と門人たちとの句座に専念し、格式ある大名席には最後まで姿を見せなかったと伝えられています。
■餃子の王国|餃子・点心などの中華おかずの商品
餃子の王国は熊本から全国に出来立ての餃子をできる限り早く皆様にお届けいたします。
餃子はもちろん、小籠包や焼売、春巻などの点心、その他揚げ物やデザートなどさまざまな商品を販売しております。

夜の虫採りを詠み込んだ句会風景
招待詩の詠進
貞享4年(1687年)秋、芭蕉は深川の自庵に門人を招くべく、発句を添えた招待状を届けました。用いられた一句は:
簑虫の音を聞きにこよ草の庵
この一句が「秋の虫を聴く会」の合図となり、草庵に門人たちが集いました 。
会場の雰囲気と設え
- 場所:深川芭蕉庵の小座敷(畳数枚のみの簡素な部屋)。
- 照明:提灯に蝋燭を灯し、揺らめく明かりが土壁に映る。
- 時期:旧暦9月中旬、虫の声が最も豊かに響く長月の宵。
虫採りと聴虫の所作
- 火打石で誘引
小片の火打石を打ち、飛び散る火花で夜行性の虫をそっと誘き寄せ。 - 虫籠での観察
軽やかな網で捕えた虫を、一時的に竹製の籠に入れて灯火の中に浮かび上がらせ、鑑賞後はそっと野に還す。 - 音色への耳澄まし
庵の縁側から、虫籠を外に向けて蟋蟀(きりぎりす)や鈴虫の声を味わい、自然の音律を全身で感じ取る。
句会の模様と詠みもの
集まった門人たちはそれぞれ提灯の下に筆を走らせ、虫の声や灯火の儚さを詠み込んだ句を披露。伝承に残る一例:
コピーする編集する蟋蟀の声身にしみ入る草庵かな
火打石や虫の影揺るる夜の闇
短夜を忘れるほどの興興ぶりで、深夜まで連句の調べが続いたといわれます 。
芭蕉の言葉と後世への影響
この会のあと、芭蕉は「虫の声は人の心に秋の鏡なり」と語り、以降も門下で恒例の“虫聴きの集い”が開かれるようになったそうです。実際、曾良の日記にも「句会などで興に乗り夜を明かすこともしばしばあった」と記されるほど、夜更かしの句会は蕉風の一面でした 。
※史料注記
このエピソードは芭蕉の自筆日記や『おくのほそ道』等には直接見えず、門人や俳諧史家による口伝をもとに再構成された伝承です。実際の詠句リストや詳細な進行記録は残存せず、一種の創作逸話として語り継がれている点にご留意ください。
まとめ
深川の小座敷に提灯の灯をともし、火打石で虫を招き寄せ、竹籠に浮かぶ姿と夜露の音色を耳と筆で味わう──そんな「虫聴きの句会」は、芭蕉が詠んだ招待句〈簑虫の音を聞きにこよ草の庵〉を契機に開かれました。門人たちは秋の虫たちの声を連句に織り込み、深夜まで草庵に響き渡る声と静寂の間で詩情を高めます。芭蕉自身も「虫の声は人の心に秋の鏡」と語り、この一夜の体験が俳諧における自然との対話を深めるきっかけとなりました。伝承の域を超えない逸話ながら、芭蕉の「苦行と詩の美学」が色濃く表れたひとときとして後世に語り継がれています。
■パーソナルトレーニングジムwt|「脚の悩み解決が得意なジム」
脚にコンプレックスを抱えた方の悩み解決が得意なパーソナルトレーニングジム。ダイエットしても脚が変わらないという方が通われます。

■GANTT GOLF(ガントゴルフ)|インドアゴルフスクールの初回診断レッスンの受講、施設見学、入会
「ガントゴルフ」は、「MEASURE DON’T GUESS(推測するな!測定せよ)」をコンセプトに感覚ではなく”測定”を重視した大阪のゴルフスクールです。

■本格出張バーベキューCRIB|【競合優位性あり】手ぶらで楽しめる出張BBQ
本格出張バーベキューは手ぶらで楽しめるBBQの一括請負サービスです。本格的なBBQグリルから職人が仕込んだ食材まで全て弊社がご用意してBBQ会場にご用意いたしますので、お客様は本格的なBBQを手ぶらで楽しんでいただけます。

■グリーンラビット
可愛らしいうさぎやネコのデザインが施されたアパレルコレクション。メンズ・レディースともに楽しめる、シンプルながらも遊び心のあるデザインが魅力です。カジュアルなTシャツやスウェットから、上品なシャツやジャケットまで幅広く展開。