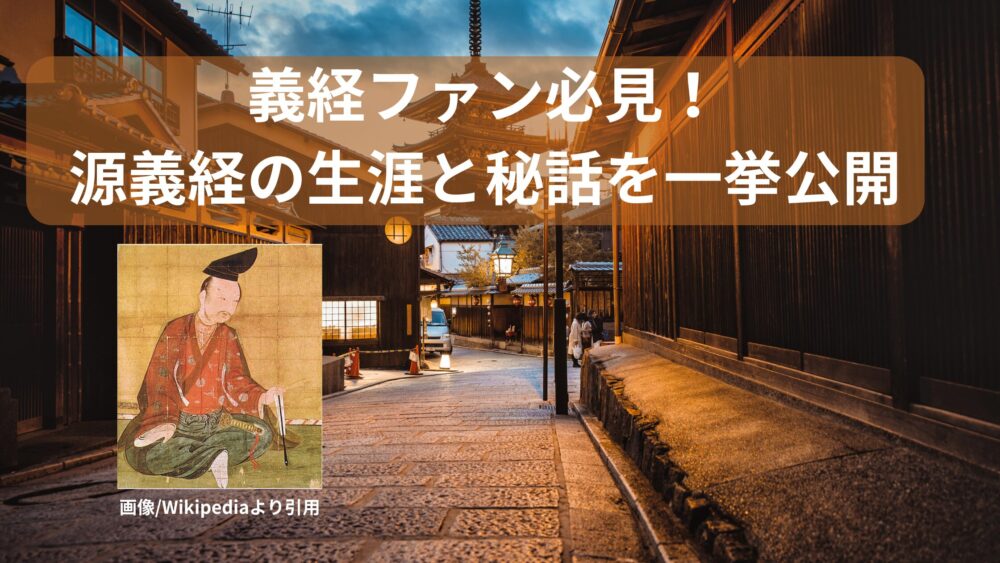一ノ谷の奇襲(1184年3月20日)
源義経は、一ノ谷の戦いで敵陣の背後にあたる険しい崖を選び、夜明け前の薄明かりのなか、わずか千数百の手勢を率いてそこを一気に降下。平氏軍がまったく予想しなかった背後からの突入で大混乱を引き起こし、わずか数千の平氏兵を逃走させる大勝利を収めました。
屋島の戦いでの焚き火作戦
元暦2年(1185年)2月19日早朝、源義経は兄・頼朝の大軍とは別行動で、和船50隻に馬50頭・兵士約150人を乗せ紀伊水道を驚異的なスピードで南下し、阿波勝浦に上陸します。【川口→屋島間約120kmを6時間で移動したという記録も残る】その後、地元豪族・近藤親家の案内で屋島背後の高松まで陸路約60kmを突進し、午前8時頃、平家の仮内裏近くに到着しました。そこで義経は、陣地を固める平家軍の士気を一気に崩すため、近隣の民家数軒に火を放ち、炎と黒煙を大規模な「焚き火」のように見せかけて「大軍が攻めてきた!」との錯覚を与えます。これにより、海からの来襲を想定していた平家軍は混乱し、戦闘準備が整わぬまま退却を余儀なくされ、義経軍はほとんど戦闘を交えることなく屋島を攻略しました。
■東京・自由が丘チョコレート専門店【チュベ・ド・ショコラ】
東京・自由が丘にあるチョコレート専門店 チュベ・ド・ショコラの割れチョコです。
壇ノ浦での「八艘飛び」伝説
壇ノ浦の戦い(元暦2年/1185年4月25日)で『平家物語』に描かれる「八艘飛び」は、以下のような逸話です。
壇ノ浦の海上戦のさなか、平家随一の猛将・平教経が源義経の大将船に乗り移り、討ち取ろうと長柄の小長刀を構えて襲いかかりました。これを察した義経は、甲冑姿のまま約二丈(約6メートル)ほどある隣の船へ身を翻って跳び移ります。その後も船から船へと飛び続け、「八艘分」跳び移ったと誇張されて伝えられるようになりました。実際には一度の跳躍が脚色された可能性が高いものの、義経の驚異的な身体能力と機転の速さを象徴する伝説として後世まで語り継がれています。
腰越で認められず書いた「腰越状」
成立の背景と日時・場所
壇ノ浦の戦い(1185年3月24日)で大勝し、平家の首領を討ち取った義経は、功績を認めてもらおうと鎌倉へ凱旋を図りました。しかし、頼朝の不興と梶原景時らの讒言によって鎌倉入りを禁じられ、東海道・腰越の満福寺に留め置かれました。その折に書かれたのが「腰越状」で、元暦2年5月24日(西暦1185年6月23日)のことと伝わります。
宛先と筆写経路
正式には兄・頼朝宛としつつも、直接の宛名には公文所別当の大江広元を記し、取り次ぎを依頼する形式をとっています。現存する伝本によれば、義経が自ら筆入れを行ったものと、側近の武蔵坊弁慶が下書きを担ったとの伝承があります。
書式と言語表現
本文は「和様漢文体」で書かれており、冒頭で自分を「左衛門少尉義経」と名乗り、勅命を受けた朝敵平家討伐の勲功を列挙。そのうえで「恐るべき讒言にあい」「莫大な勲功を黙殺され」などと、自らへの誹謗中傷を嘆きつつ、血の涙にくれる弟としての心情を飾らず率直に綴っています。
主な文面内容(抜粋現代語訳)
「忠言は耳に逆らうと言われますが、私には何一つ罪はなく、ただ弟の義を示す機会を奪われ、日を追うごとに無念の思いに胸が痛みます。前世の悪業か、運命のいたずらか、今ここで兄上の御顔を拝せぬままでいることは、血を分けた肉親として我が身の存在をも疑うほどの悲しみです。」
といった、誠実さと慟哭が響く言葉が並びます。
その後の顛末と史料的意義
大江広元らを通じて頼朝に提出されたものの、結局義経の鎌倉上洛は許されず、義経は京都へ引き返すことになります。以降、「腰越状」は手習いの書道教材としても用いられ、和漢折衷の書式や筆づかいの良い見本として明治期まで広く流布しました。現在、満福寺や各地の写本にその筆写が残り、文学資料・史料として高く評価されています。
■犬・猫のために作ったペット用品ブランド【ONEKOSAMA OINUSAMA】
おねこさまもおいぬさまも家族の一員! その思いを胸に、赤ちゃん向け商品と変わらない丁寧で優しいもの作りを おねこさま・おいぬさまとご主人さまのためにお届けします。
天狗から授かった「羽団扇(はうちわ)」の術
授与の場面(鞍馬寺・僧正ヶ谷にて)
幼名・牛若丸(後の義経)が7~8歳のころ、父・義朝没後の養育先である京都・鞍馬寺に預けられました。山中深くの僧正ヶ谷で、地元の豪勇とされる大天狗「鞍馬山僧正坊」と出会い、剣術・兵法だけでなく、神通力を秘伝として伝授されます。この際、羽団扇の術も授かったと伝わります。
羽団扇の外観と素材
羽団扇は、鷹や鷲などの猛禽類の羽を奇数枚(社寺によって9枚、11枚、13枚など)束ね、木製の柄に取り付けた大扇子状の法具です。柄は檜や樫が用いられ、羽は厳選された上質のものが使われます。
術の主な効果
- 風の制御:扇を大きく振ることで突風を起こし、弓矢の射程や速射性を飛躍的に高める。
- 火勢の煽動:焚火や松明の炎を強め、大規模な焚き火作戦や夜戦での攪乱に利用。
- 幻術・分身:霧や煙を発生させて敵の視界を遮り、自身の姿を分身のように見せる。
- 結界の形成:扇を立てて座すだけで妖魔退散の結界を張り、陣中の安全を確保。
- 縮地・飛行補助:天狗の飛行術を学んだ身として、地面を“縮める”かのような俊敏な動きを可能にする。
実戦での応用例(伝承)
義経が戦場で扇を用いた具体的記録は乏しいものの、屋島の焚き火作戦や壇ノ浦の潮流制御など、風や火を味方にした奇襲戦術はこの羽団扇の技法と結びつけて語られることがあります。
後世への伝承と文化的影響
- 能「鞍馬天狗」や浮世絵にも羽団扇を手にした天狗像が描かれ、義経伝説の一要素として定着。
- 鞍馬電鉄(現・京都バス)の社章にも羽団扇の意匠が取り入れられ、地域文化のシンボルに。
まとめ
源義経は、平安末期の武士として兄・頼朝と並び称されるほどの名声を誇りながらも、その生涯は鮮やかな戦術と悲劇に彩られています。幼少期に鞍馬山で天狗・僧正坊から剣術だけでなく「羽団扇」の術を授かり、風や炎を操る秘技を学んだと伝わります。1184年の一ノ谷の戦いでは、夜明け前の薄明かりを突いて背後の崖から奇襲をかけ、大勝利を収めました。続く1185年の屋島の戦いでは、あえて民家に火を放った大規模な焚き火作戦で平氏軍を撹乱し、わずかな戦闘で制圧。また壇ノ浦の海戦では、敵の間を甲冑姿で船から船へ跳び移る「八艘飛び」の伝説を生み出しました。戦後、兄頼朝の疑念により鎌倉入りを禁じられた義経は、満福寺で漢詩体の「腰越状」をしたため、忠誠と無念を率直に綴りますが、その嘆願は叶わず京都へ引き返すことに。波乱に満ちた数年の活動後、義経の行方は諸説を残しつつも、彼の巧妙な戦術と天狗譚は能や浮世絵にも影響を与え、今日まで語り継がれています。
■国内トップクラスの実績!防災セットメーカーLA・PITA直営サイト【アットレスキュー】
国内実績トップクラスの防災セットメーカーLA・PITAが開発した防災セットがズラリ! TVや雑誌など各メディアでも取り上げられている話題の「防災セットラピタ」もおすすめ!
■楽器や2ヵ月分のお月謝が無料に!子供の音楽・バレエ・ダンス教室【EYS‐kids】
幼児から小学生まで、早期高度教育として音楽・ダンス・バレエなど様々な習い事をご提供! 「上手くなる」「楽しむ」はもちろん、「将来生かせるアート思考を育むこと」にこだわっています!
■【Travelist(海外格安航空券)】
海外航空券がお得に買える! 認可代理店だから安心して購入できる。
■グリーンラビット 可愛らしいうさぎやネコのデザインが施されたアパレルコレクション。メンズ・レディースともに楽しめる、シンプルながらも遊び心のあるデザインが魅力です。カジュアルなTシャツやスウェットから、上品なシャツやジャケットまで幅広く展開。