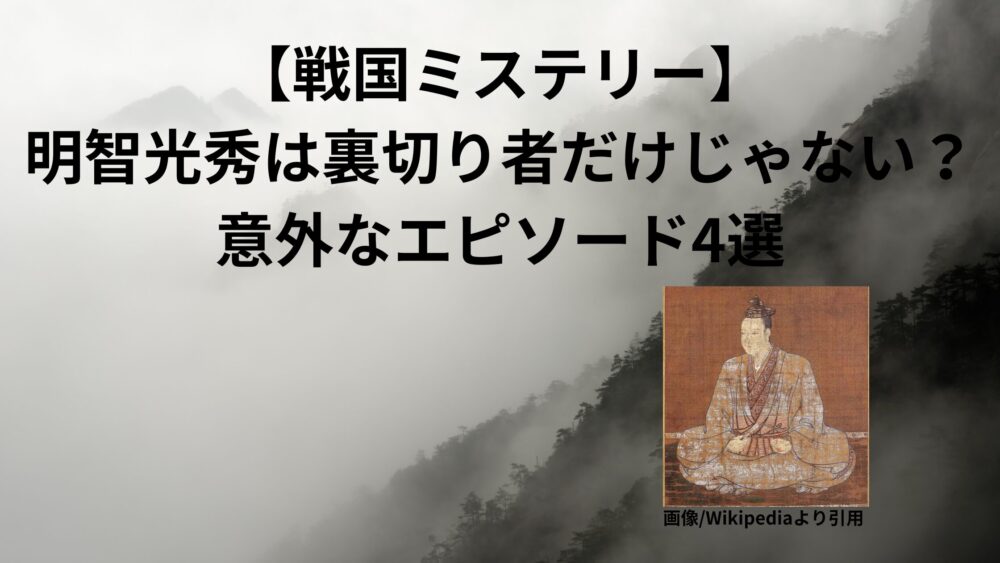「本能寺の変」で織田信長を討った、歴史最大級の裏切り
1582年(天正10年)、明智光秀は主君・織田信長に反旗を翻し、京都の本能寺に滞在していた信長を急襲して自害に追い込みました。これが日本史上でも屈指の大事件、「本能寺の変」です。
この行動は、誰もが予想しなかった“家臣による主君暗殺”であり、戦国時代の常識を覆すクーデターでした。光秀はその後、天下を手にしようとしますが、わずか11日後に羽柴秀吉に討たれたことから、「三日天下」とも呼ばれる儚い権力の象徴にもなっています。
本能寺の変の動機については、未だに「怨恨説」「野心説」「黒幕説」などさまざまな説があり、今なお研究者や歴史ファンの関心を集めています。
“本能寺の変”直前に「徳川家康を接待していた」⁉
ー 謀反の前日まで、光秀は“おもてなし役”だった ー
1582年(天正10年)6月、織田信長は天下統一の総仕上げとして、中国地方の毛利攻めに出陣していた羽柴秀吉を支援するため、上洛(じょうらく)します。
その際、信長は「明智光秀に徳川家康の接待役を命じる」という任務を与えました。
家康はこの時、織田信長からの招きを受けて上洛しており、側近の本多忠勝らとともに安土城を訪れたばかりでした。信長は自身の滞在する本能寺を出て、毛利攻めへ向かうため、家康の対応を光秀に任せたのです。
光秀は非常に丁寧なもてなしを行っていたとされ、京都・堺方面を案内し、警護まで手配。宿所の安全管理などを徹底的に担いました。
これは、信長が家康を“同盟者以上の重要人物”と見ていた証拠であり、それだけ信頼できる家臣として光秀が選ばれていたとも言えるでしょう。
ところが――
この家康接待の任務が終わった直後、光秀は突如として軍を率い、主君・信長の待機する本能寺を襲撃したのです。6月2日未明、「本能寺の変」が発生。
もし光秀が家康をも討っていれば、のちの「江戸幕府」は存在しなかったかもしれません。
しかし家康は、異変を察知するとすぐに堺を出発し、命からがら伊賀越えで三河国に逃げ延びました。この“脱出劇”も後に語り継がれる名場面です。
▶ なぜ家康を討たなかったのか?
この点は、歴史上最大の謎の一つとされています。
- 家康と争う意図はなかった
- 時間的・軍事的余裕がなかった
- 家康を討つことで信長暗殺の意図がばれるリスクを避けた
など諸説あります。
しかしいずれにせよ、家康を見逃したことが、結果的に光秀自身の「天下奪取」の道を閉ざすきっかけとなったのです。
■SNSで話題の芋スイーツ 九州産紅はるか焼き芋の紅茶房(べにさぼう)
九州産の紅はるかの焼き芋の産地別の食べ比べが楽しめます。 九州各地で育ったベニハルカを使用し、それぞれの地域の特性を活かした焼き芋を提供しています。
「水墨画」に秀でた文化人だった?
― 武将にして文人、明智光秀のもうひとつの顔 ―
明智光秀といえば、一般的には「本能寺の変で信長を討った裏切り者」というイメージが強いですが、実は教養あふれる文化人としての一面を持っていた人物でもあります。その中でも特筆すべきは、「水墨画」に通じていたという点です。
◆ 教養武将としての背景
光秀は若い頃、浪人生活を送る中で京都や堺に滞在し、禅僧や公家、文化人たちと交流を深めていたと伝わります。彼の教養レベルは当時の武士の中でも非常に高く、和歌、連歌、茶道、書、さらには水墨画にまで精通していたことが知られています。
戦国武将の中でも、これだけ多様な文化活動に関わった人物は珍しく、「文化系武将」としての光秀像は、近年再評価されつつあります。
◆ 水墨画との関係
光秀が描いたとされる水墨画は現存していませんが、「山水画をたしなんだ」「絵心があった」という記録が複数の古文書に見られます。また、光秀の家臣や家族にあたる者たちにも、文芸や書画に秀でた者が多くいたことから、彼の屋敷には文人サロン的な空気があったとも推察されています。
また、光秀が築いた坂本城(近江)は、湖畔にたたずむ美しい城として知られ、その構造や庭園には美意識が強く反映されていたとも言われています。光秀はこの坂本城に多くの文化人を招いており、茶会や詩会、画会(がかい)などを催していた記録も残っています。
◆ 「武」の人ではなく「文」との融合
光秀が仕えた足利義昭や織田信長はいずれも文化を重んじる人物でしたが、特に光秀はそうした「文の価値」に共鳴していた武将の一人です。
例えば、茶人・津田宗及(つだそうぎゅう)の日記には、光秀が催した茶会や文化的交流の記述が見られます。これは単なる“客人としての付き合い”ではなく、光秀自身が文化人として認められていたことを示唆します。
◆ まとめ:戦国武将にして芸術家の面影
「本能寺の変の主役」という劇的な事件の陰に隠れがちですが、明智光秀のもう一つの顔――それは、戦を操るだけでなく、筆でも心を描いた文化人の姿です。もし彼が天下を取っていたら、日本の芸術文化にまた違った影響を与えていたかもしれません。
実は「長男」を討たせていた?父子の悲劇
― 本能寺の変が引き裂いた、明智家の親子の絆 ―
1582年6月2日、明智光秀は“本能寺の変”で織田信長を討ち、日本全国に衝撃を与えました。しかし、この謀反が引き起こしたのは政治的混乱だけではありません。光秀自身の「家族」も巻き込まれ、悲劇的な最期を迎えることになります。
◆ 長男・明智光慶とは誰か?
明智光秀の長男とされる人物には諸説ありますが、「明智光慶(みつよし)」または「明智光春」という名で伝わっており、当時は若年ながらも、丹波亀山や近江坂本などの城の守備を担っていたとされます。
光慶は本能寺の変後、光秀が羽柴秀吉との対決(山崎の戦い)に向かう際、留守を守る役目を担っていました。しかし光秀が敗れると、彼の息子や重臣たちは織田家に恨みをもつ者たちによって次々と討たれていくのです。
◆ 坂本城の最期 ― 家族一族が自害
特に有名なのが、光秀の居城・坂本城(近江)での出来事です。
山崎の戦い(6月13日)で光秀が敗死した後、その知らせを受けた坂本城の守備隊は、もはや降伏すら許されない状況に追い込まれました。そして、光慶を含む明智一族や家臣たちは、城に火を放ち、集団自害したとされています。
このとき、光秀の妻・熙子(ひろこ)もいたとされ、一家全滅に近い形で滅んだのです。つまり、光秀の決起によって、自らの手で「一族の命」をも葬ることとなったわけです。
◆ 光秀はそれを知っていたのか?
これは現在でも議論の対象ですが、本能寺の変前後、光秀は息子を要衝の城に配置するなど、信頼を寄せていた形跡があります。しかし謀反によって織田家の強烈な反撃を受けることは容易に想像できるため、ある程度の覚悟はしていた可能性もあります。
ただし、謀反の直後から秀吉の動きがあまりに早く、光秀がこれほど早期に敗北するとは予想していなかったとも考えられます。結果的に、息子を「討たせる」形になってしまったことは、皮肉な運命といえるでしょう。
◆ 「父子の悲劇」としての歴史的意義
この出来事は、単なる政変ではなく、親子や家族という個人的な関係が、政治の渦に飲み込まれていく戦国時代の非情さを象徴しています。
明智光秀は「理想主義者」とも「冷酷な策士」とも語られますが、たとえ天下を狙ったとしても、自らの血を分けた家族すら守れなかった現実は、彼の人生における最大の悲劇かもしれません。
■東京・自由が丘チョコレート専門店【チュベ・ド・ショコラ】
各種ショッピングモールでも人気の割れチョコの元祖です。 東京・自由が丘にあるチョコレート専門店 チュベ・ド・ショコラの割れチョコです。
明智姓」は本当は“名乗り”だった?
― 戦国武将・明智光秀の「出自」に隠された謎 ―
明智光秀といえば、“明智姓”で広く知られていますが、実はこの「明智」という姓が正式な家系に基づいたものかどうかについては、近年の研究でさまざまな議論が交わされています。
結論から言うと、光秀が「明智姓を名乗っていたことは確か」ですが、その血統の裏付けがはっきりしない=戦略的に“名乗った”可能性が高いというのが現在の有力説です。
◆ 一応の通説:土岐氏の支流・明智氏の出身
史料や系図上では、光秀は「美濃国(現在の岐阜県)・明智荘(あけちのしょう)」に由来する土岐氏の庶流「明智氏」の出身とされています。
土岐氏は室町時代に美濃守護を務めた名門であり、明智氏はその分家。そのため、光秀が「明智姓」を称していたことは、ある程度正当性があるように見えます。
しかしこの「明智氏出身説」には、以下のような弱点があります。
◆ 家系図が曖昧・同時代史料に乏しい
光秀の出生を示す一次史料(当時の公式文書)がほとんど存在しておらず、後世の軍記物や系図に頼る部分が大きいのです。
たとえば、江戸時代に成立した『明智軍記』などは光秀を「土岐明智氏の名門の末裔」と記していますが、同時代の記録ではそれを裏付ける明確な証拠がありません。
また、土岐氏本家の家系との接点や記録も極めて薄く、光秀が“後から自称した可能性”が浮上してくるわけです。
◆ 戦国時代の「名乗り」は柔軟だった
戦国時代の武士たちは、必ずしも血縁や出生地に基づいて姓や名字を名乗っていたわけではありません。自らの立場を高めるため、あるいは権威づけのために“名乗る”ことがよくありました。
たとえば:
- 自分が仕える有力家臣の支流を名乗る
- 由緒ある家の名を借りて自家の格を上げる
- 所領や居住地の地名を名乗りとする
これらはごく一般的なことでした。つまり、光秀が「明智姓」を名乗ったのは、“土岐一門であることをアピールするため”の戦略的名乗りであった可能性があるのです。
◆ 斎藤道三家臣時代の資料に「明智」の表記が少ない
光秀は美濃の戦国大名・斎藤道三の家臣だった時期がありますが、その頃の史料には「明智光秀」という名前があまり登場しません。
彼が「明智」の名を本格的に用い始めたのは、織田信長に仕えて以降である可能性が高いとも言われており、ここでも「名乗りの意図的操作」が感じられます。
◆ まとめ:明智光秀の「明智姓」は、“自己演出”だった?
「明智光秀」という名前は今日では定着していますが、その姓の由来には実は不確かな部分が多く、「名門・土岐明智氏の出」というのは、政治的な自己演出の一環だった可能性があります。
この背景には、「名門の出自」を示すことで信長や朝廷、公家との関係性を強化しようとした、光秀自身の高度なセルフブランディング戦略があったのかもしれません。
まとめ
織田信長を討った「本能寺の変」で知られる明智光秀。その名は“裏切り者”として歴史に刻まれましたが、その実像は一面的ではありません。
本能寺の変直前には徳川家康を接待しており、文化人としては水墨画や和歌に通じた教養人。そして、謀反によって自らの息子までも悲劇に巻き込んだ父としての苦悩。さらに、名乗った「明智姓」には出自の曖昧さや自己演出の意図も見え隠れします。
これらのエピソードは、光秀が単なる「反逆者」ではなく、複雑な背景と深い人間性を持った人物であったことを物語っています。
史実の裏にある「もうひとつの光秀像」に触れることで、戦国史の面白さがより深く味わえるのではないでしょうか。
■創業89年・京都の伝統の味を召し上がってみませんか?
【しば漬け風味おらがむら漬】をはじめ、伝統野菜の聖護院かぶら、すぐき、壬生菜、日野菜、水茄子など、季 節のおいしいお野菜を、 浅漬けや、さっぱりとした酢漬け、糠漬け、醤油漬け、奈良漬け等、野菜に合った漬け込みをしております。
■全国の美味しい特産品に特化したふるさと納税サイト【ふるさと本舗】
ふるさと本舗は 、全国の美味しい特産品に特化したふるさと納税ポータルサイトです。 ブランド和牛やカニ、シャインマスカットなど 普段はちょっと手が出せない美味しい特産品を取り揃えています。
■日本酒ファンが選ぶ地酒専門店!業界最大級!各メディア掲載実績多数あり【矢島酒店】
1963年創業。日本全国の蔵元を訪ね、 200蔵を超える蔵元と2000種類以上の銘柄を取り揃えた 地酒専門店「矢島酒店」によるECサイト
■グリーンラビット
可愛らしいうさぎやネコのデザインが施されたアパレルコレクション。メンズ・レディースともに楽しめる、シンプルながらも遊び心のあるデザインが魅力です。カジュアルなTシャツやスウェットから、上品なシャツやジャケットまで幅広く展開。