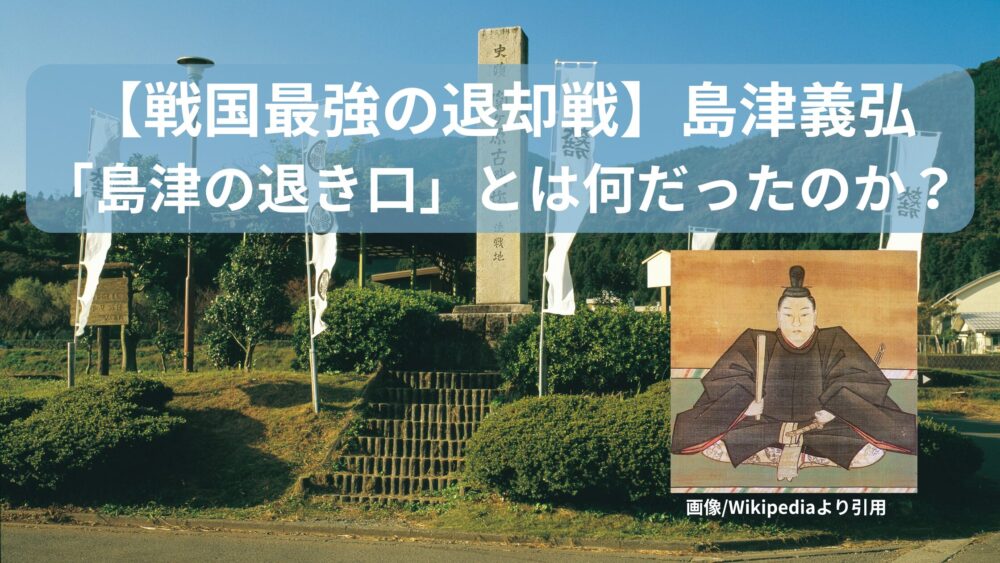島津義弘の最も有名な話のひとつは、「関ヶ原の戦いでの敵中突破(島津の退き口)」です。
🔥【島津の退き口】とは
1600年の関ヶ原の戦いで西軍に属していた島津義弘は、味方の敗北が決定的になる中、逃げ道を絶たれ孤立します。通常なら降伏か自害という状況で、義弘はあえて徳川本陣の中央を真っ向から突き破るという前代未聞の決断をします。結果、義弘は少数の家臣と共に敵中を突破し、薩摩までの帰還に成功。
この行動は「島津の退き口」として語り継がれ、義弘の胆力と武勇の象徴となっています。
朝鮮出兵で「鬼石曼子(グイシーマンズ)」と恐れられた
🔥島津義弘、「鬼石曼子(グイシーマンズ)」と恐れられた理由
文禄・慶長の役(1592〜1598年)、豊臣秀吉の命により日本軍が朝鮮半島へ出兵した際、島津義弘はその中でも特に恐れられた武将でした。
島津軍は少数精鋭・鉄壁の防御・強烈な突撃戦法を得意とし、特に義弘の軍は“討ちもらした敵は一人も帰さぬ”と言われるほど徹底した殲滅戦を展開していました。明軍や朝鮮軍は、この異常な戦闘力と徹底的な追撃を目の当たりにし、島津義弘を「鬼のように恐ろしい島津」=鬼石曼子(グイシーマンズ)と呼んだのです。
この「鬼石曼子(鬼島津)」という異名は、漢字をあてがったもので、“鬼”はその猛々しさ、“石曼子”は“島津”を音写したものと考えられています。つまり、「鬼の島津」という意味です。これは単なる侮蔑ではなく、敵からも“化け物じみた強さ”を認められた証拠でした。
さらに義弘は戦場では常に最前線に立ち、自ら刀を振るい、兵たちの士気を鼓舞していたとされます。泗川の戦いなどで明軍を壊滅させた戦術も恐れられ、島津軍の動向が敵側にとって大きな脅威となっていたことが、記録にも残されています。
■【高単価スイーツ】SNSで話題の芋スイーツ 九州産紅はるか焼き芋の紅茶房(べにさぼう)
九州各地で育ったベニハルカを使用し、それぞれの地域の特性を活かした焼き芋を提供しています。 収穫後、芋は泥付きのまま1,000時間以上かけて熟成させ、 低温でしっくり焼き上げることで自然な甘みを最大限に引き出しています。
撤退戦で伝説を残した「泗川の戦い」
🛡 泗川の戦い(1598年)|島津義弘の伝説的撤退戦
■ 背景
泗川の戦いは、1598年の慶長の役の末期、朝鮮半島南部・泗川(現在の韓国・晋州市近郊)にて行われました。この時、島津義弘は約7,000の兵を率いて泗川に駐屯しており、撤退命令を受けて釜山方面へ下がる途中でした。
しかし、そこに待ち受けていたのが、明・朝鮮の連合軍 約6万人以上。義弘の軍は数で劣り、しかも敵は山を背にし、包囲の構えを見せるという絶望的な状況に置かれました。
■ 義弘の対応:あえて「待ち受け」の陣を張る
通常なら撤退・防衛に徹する場面ですが、義弘はあえて泗川の城外に陣を張り、敵を迎え撃つ構えを取ります。この大胆な決断は、敵を油断させる狙いがありました。
義弘は城の構造や地形を活かし、敵の進行ルートを誘導しつつ、逆に包囲を逆手にとって各個撃破するという戦術を採用。山の斜面や谷間に伏兵を配置し、敵が一斉に攻め込んできた瞬間を見計らって挟撃(きょうげき)作戦を展開します。
■ 結果:6万の大軍を壊滅させる大勝利
この戦術が見事に決まり、明・朝鮮連合軍は大混乱に陥ります。島津軍の激しい反撃により、連合軍は数千〜数万人規模の戦死者を出し、総崩れとなって撤退。島津軍側は数百人程度の損害で勝利しました。
この戦いは、義弘の冷静な判断力・戦術眼・指導力が発揮された戦例として、「撤退戦での奇跡的勝利」として語り継がれています。
■ 明・朝鮮側の記録にも残る“恐怖の島津軍”
特筆すべきは、泗川の戦いにおける島津軍の強さが敵側の記録にも克明に記されていることです。明軍の文書では、島津軍の激しい反撃により味方が混乱し、「まるで鬼の軍勢に襲われたようだった」と記述されるほど。その後、敵軍は「島津軍とは交戦を避けるべき」と認識するようになりました。
■ 泗川の戦いの意義
この戦いは単なる勝利ではなく、島津義弘の軍事的天才ぶりが証明された瞬間です。また、この勝利があったからこそ、島津軍はその後の安全な撤退を成功させ、日本本土への帰還を果たすことができました。
関ヶ原の戦いで“敵中突破”という前代未聞の離脱劇を成功させた
⚔ 関ヶ原の戦いにおける島津義弘の“敵中突破”|伝説の撤退戦「島津の退き口」
■ 関ヶ原の戦いと島津義弘の立場
1600年9月15日、天下分け目の戦いとされる「関ヶ原の戦い」が勃発。島津義弘は西軍(石田三成陣営)に属していましたが、西軍の主力とは距離を置いて東南の位置に布陣していました。これは義弘が石田三成に対して懐疑的で、積極的に協力する意志がなかったためとされています。
実際、戦が始まってもしばらく島津軍は動かず、戦局が東軍有利に傾いても独自の判断で行動していました。
■ 惨敗と孤立、逃げ道はなし
西軍の敗北が決定的になると、多くの大名が戦場を離脱します。しかし、島津義弘は家臣に「敗走することは島津家の恥」と述べ、退却命令を出さず、自ら最後まで戦う決意を固めていました。
しかし実際にはすでに四方を敵に囲まれ、通常の撤退路はすべて塞がれていました。まさに絶体絶命の状況です。
■ 驚愕の決断:敵の本陣を“真っ向突破”
そこで義弘が下した決断は、敵のど真ん中、つまり徳川家康の本陣を突破して撤退するという、前代未聞の策でした。
これは戦術的には「自殺行為」に等しい作戦でしたが、家臣たちも覚悟を決め、義弘の決断に従います。そして、わずか約80騎ほどの兵で徳川本陣の中核に突撃。
この時、島津軍は義弘の影武者を複数立てて進軍し、敵の混乱を誘いながら中央突破に成功したとされています。また、家臣の島津豊久(義弘の甥)や鎌田政近らが盾となり、自らの命を犠牲にして義弘を逃がしたことも知られています。
■ 逃げ切った島津軍、薩摩へ帰還
島津軍は多くの犠牲を払いながらも、最終的に義弘を無事戦場から離脱させ、伊勢・紀伊を経由して薩摩に帰還することに成功します。この伝説的な撤退劇は「島津の退き口(のきぐち)」と呼ばれ、戦国史における最も劇的な離脱戦の一つとされます。
■ 徳川家康の対応とその後
驚いたのは徳川家康です。家康は義弘のあまりの胆力と戦術に感服し、「この男には手を出すべきではない」と判断したともいわれています。事実、家康は義弘に出頭を命じたものの、それ以上の追及はせず、島津家は存続を許されたのです。
■ 歴史的意義
「島津の退き口」は、単なる撤退戦ではなく、武士の誇りと忠義、そして冷静な判断力が融合した戦国時代屈指の離脱戦として語り継がれています。この撤退を可能にしたのは、義弘の決断と、彼を信じて命を賭けた家臣たちの忠誠心にほかなりません。
■『お母さんの笑顔が咲く、京つけものの贈り物。』
【しば漬け風味おらがむら漬】をはじめ、伝統野菜の聖護院かぶら、すぐき、壬生菜、日野菜、水茄子など、季 節のおいしいお野菜を、 浅漬けや、さっぱりとした酢漬け、糠漬け、醤油漬け、奈良漬け等、野菜に合った漬け込みをしております。
家康に降伏せず、薩摩に帰還しても“勝者の風格”を保った
🏯 島津義弘、徳川家康に降伏せず「勝者の風格」を保った理由
■ 関ヶ原の戦い後、義弘の立場は“敗軍の将”だった
1600年の関ヶ原の戦いで西軍が敗れ、徳川家康が天下人としての地位を固める中、西軍の主だった大名たちは次々と降伏や出頭を余儀なくされました。毛利輝元や上杉景勝らも家康に臣従し、その領土の維持を図ったのです。
島津義弘も西軍の武将でしたが、他の武将とはまったく違う対応を取りました。それは――「家康に一度も面会せず、薩摩に帰還したまま出頭を拒否し続けた」という姿勢でした。
■ 家康の出頭命令を“無視”した義弘の胆力
戦後、家康は義弘に対して出頭を命じましたが、義弘はこれを無視します。義弘は家康に手紙を送ることはあっても、直接面会することは決してせず、代わりに嫡男・島津忠恒を江戸に使者として送りました。
これは明らかに、「薩摩藩としては従属の姿勢は示すが、義弘自身は家康に頭を下げぬ」という島津家の独自性と武士の誇りを貫いた対応でした。
■ 家康も追及を避けた「不問」の判断
本来ならば謀反の罪で断罪されてもおかしくない立場でしたが、徳川家康は島津義弘に対して処罰を下しませんでした。その理由として、以下のような点が挙げられます:
- 義弘が関ヶ原の本戦であまり積極的に西軍に加担していなかった(戦闘中も静観していた)。
- 中央突破の「島津の退き口」に家康自身が感服し、下手に追及すれば反発を招くと考えた。
- 薩摩は地理的に遠隔地であり、直接統制が難しかったこと。
- 義弘の政治的処世術――「出頭せず、しかし一応の書簡上の謝罪」は絶妙なバランスだった。
つまり、家康は義弘に“勝ちを譲る形”で不問としたのです。
■ “敗者”でありながら“勝者のように”振る舞う
薩摩に戻った義弘は、敗戦の将として恥じるどころか、堂々とした態度で藩主としての責務をまっとうします。家臣たちの前でも「戦は負けたが、武士としての誇りは守った」と語ったとされ、薩摩藩内ではむしろ尊敬を集めました。
さらに、義弘が関ヶ原から帰還した際には、城下の民が道に並び、「よくぞ戻られた」と称賛を送ったという記録もあり、“敗者”ではなく“英雄”として迎えられたのです。
■ 歴史的評価:「義をもって家康に屈せず」
義弘の対応は、戦国時代でもまれに見る“勝者に従わない敗者”として後世に語り継がれました。これは単なる頑固さではなく、独立を重んじる薩摩武士道と、戦いにおける礼節・信念を貫いた行動として高く評価されています。
結果として島津家は改易もされず、江戸時代を通じて薩摩藩77万石を維持し、幕末の雄藩へと繋がっていきます。
まとめ
島津義弘は、朝鮮出兵で「鬼石曼子」と恐れられるほどの武勇を発揮し、泗川の戦いでは圧倒的な敵軍を撃退するという奇跡を成し遂げました。関ヶ原の戦いでは敵中突破という前代未聞の離脱劇を成功させ、戦後も徳川家康に頭を下げることなく薩摩に帰還し、武士としての誇りと“勝者の風格”を保ち続けました。
その生涯は、単なる戦上手にとどまらず、信念と胆力を兼ね備えた“真の武将”として、今なお多くの人々に尊敬されています。
■創業65年超の海鮮問屋が良質なカニ・うなぎをお届け!
年間10万箱以上販売の大人気商品「元祖カット済生ズワイガニ」をはじめ カニ専門店として、良質なカニを多数ご用意しており、 厳選した国産うなぎを焼きにこだわりふっくら柔らかな食感を残したまま香ばしく焼き上げ お届け致します!
■自然と共に生きるみつばちが、毎日の笑顔をつくります【武州養蜂園】
武州養蜂園は埼玉県熊谷市を拠点とし生産から販売まで一貫しておこなっている純粋はちみつ、 はちみつ加工品、ローヤルゼリー、プロポリス等の生産販売をしています。
■おうちをレストランに変える食ブランド【TastyTable FOOD】
手作りだからこそできる味の調整や、絶妙な火の加減、 機械製法では再現できない時間をかけての丁寧な作り込みを行っています。
■グリーンラビット
可愛らしいうさぎやネコのデザインが施されたアパレルコレクション。メンズ・レディースともに楽しめる、シンプルながらも遊び心のあるデザインが魅力です。カジュアルなTシャツやスウェットから、上品なシャツやジャケットまで幅広く展開。