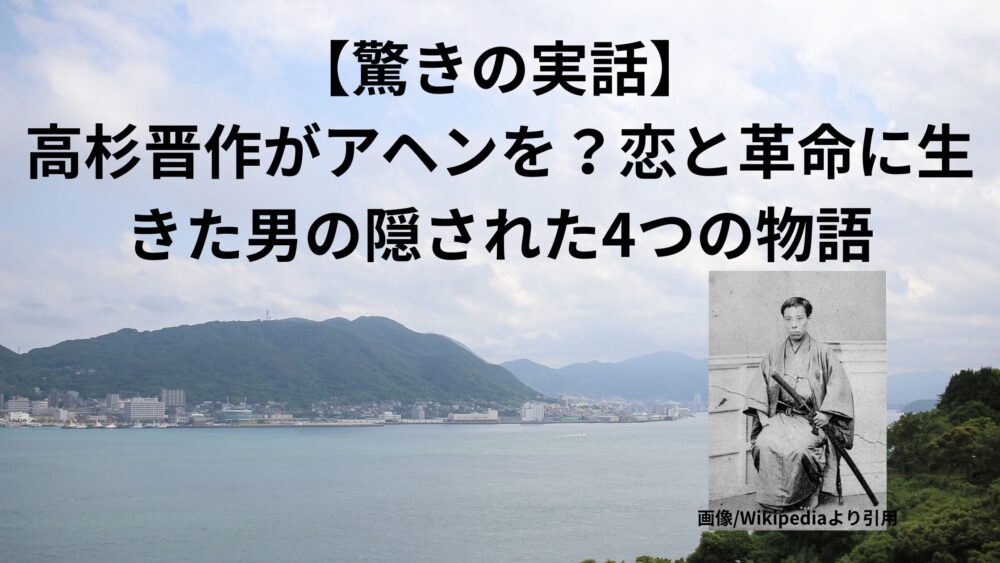■ 功山寺挙兵(こうざんじきょへい)――奇兵隊の創設者、命を賭した大逆転劇
1864年、高杉晋作は長州藩内の保守派(俗論党)によって失脚し、下関に潜伏していました。
その頃、藩は幕府との戦争(第一次長州征伐)を避けるために恭順路線を選び、尊王攘夷派は追われる立場に。
しかし、晋作はその流れを「長州が長州でなくなる」と見て、決起を決意。
翌1864年12月15日、下関・功山寺にて、わずか約80名の同志を率いて挙兵します。
「奇兵隊」など諸隊もこれに呼応し、長州藩内は一気に形勢逆転。
数ヶ月後には保守派が失脚し、晋作ら尊攘派が藩政を掌握しました。
この功山寺挙兵は、わずかな人数で藩の主導権を奪還した奇跡的な反乱として知られ、後の倒幕運動の土台を築いた象徴的な事件です。
実は「長州一のモテ男」だった?
■ 遊郭の女性「おうの」との切ない恋
晋作の女性関係で最も知られているのが、下関の遊女「三味線屋おうの」との関係です。
彼は奇兵隊を率いて奔走する合間にもおうののもとを訪れ、心の安らぎを求めていたとされます。
おうのは単なる恋人ではなく、晋作の生活面を支え、病の療養時には看病にも当たりました。晋作が京都や下関で潜伏中も、彼女は影のように寄り添い続けたと伝えられます。武士の身でありながら遊女との交際を貫いた晋作は、形式や身分に縛られない自由な恋を貫いた男でもありました。
晩年、病に伏した晋作のそばにはおうのがいて、彼の最期も看取ったという説もあります。
それは、単なる一時の情事ではなく、「死を前にした魂の伴侶」とも言える関係性でした。
■ 彼に惹かれた女性たち
晋作の周囲には、彼に心を寄せた女性が複数いたことも知られています。正妻・雅子との仲は形式的なものであったとも言われていますが、晋作の魅力に惹かれた女性たちは、身分や立場を問わず多かったと記録にあります。
たとえば、長州藩の奥向きの女性の中には、彼を一目見ただけで心を奪われたという逸話もあるほどで、晋作の名が女性たちの間で“憧れ”として語られていたことがうかがえます。
■ 「色男」でありながら信念を貫く男
晋作の“モテ”は、単に外見の魅力だけでなく、
「人のために命を投げ出す覚悟」
「理想を現実に変える行動力」
「言葉に嘘がない誠実さ」
といった、男としての“真の色気”に裏打ちされていたものでしょう。
遊郭の女性にさえ「あなたのような人のそばで生きたい」と言わせた男――
それが高杉晋作です。
■腰に優しい敷布団 極厚17cm【雲のやすらぎプレミアム】敷布団
テレビ局各社で大絶賛!雑誌でも特集が組まれ、 全国のお客様から満足度の高いクチコミを頂いている注目度抜群の敷布団です。 「雲のやすらぎ」シリーズでこだわり抜いたのは『雲の上に浮いてるような感覚』です。
アヘンを使って療養していた?
■ 若くして命を奪った病――「肺結核」
高杉晋作が命を落としたのは、わずか30歳という若さでした。
その原因は、当時「不治の病」とされた肺結核(痨病・ろうびょう)です。
幕末の日本では、衛生環境が悪く、栄養状態も不安定だったため、結核は庶民から武士、知識人に至るまで広く流行していました。咳、発熱、喀血、体重減少を伴い、徐々に衰弱していくこの病は、多くの若者を命の危機に追い込みました。
晋作も激務の中で体を壊し、咳が止まらなくなり、次第に寝たきりの状態となります。
■ アヘンは“医薬品”だった時代背景
現在では違法薬物として認識されているアヘン(阿片)ですが、19世紀の日本では医療用鎮痛・鎮咳薬として広く使われていました。
幕末の医療では、アヘンは西洋からもたらされた「最新の薬」であり、特に結核患者にとっては痛みや咳を和らげる“救世主”のような存在だったのです。
漢方薬としても「阿片丸」などの名称で市販され、江戸の町医者も処方していた記録がありました。
■ 高杉晋作とアヘン――証言と使用の実態
晋作がアヘンを使っていたという話は、複数の記録や証言から裏付けられています。
なかでも、親しかった僧侶や家人の証言では、「夜間の咳を抑えるために阿片を炙って服用していた」という記述が残っています。
晋作は死の1年前から、急激に体調を崩し、布団の上から動けない日も多くなりました。しかし、病床にあっても彼は政治的書簡を送り続け、同志と会話し、時には激しく語気を強める場面もあったといいます。
そんな彼の活動を支えていたのが、“最低限の咳を抑えるアヘン”だったのです。
■ 依存ではなく「意志のための使用」
もちろん、アヘンには依存性がありましたが、晋作の場合は快楽や逃避のためではなく、「動くための、闘うための」使用だったと考えられています。
苦しみながらも藩政に意見を出し、奇兵隊や同志を鼓舞し続けた彼の姿は、薬に頼るだけの病人ではなく、命を削りながら最後の一瞬まで「志」を貫いた男でした。
■ まとめ:幕末の現実が映し出す“弱さの中の強さ”
高杉晋作がアヘンを用いたという事実は、単に「薬に頼った」という話ではありません。
それは、幕末という激動の時代を生き抜き、死と隣り合わせの状況でも最後まで理想を捨てずに動き続けた「強さ」の象徴でもあります。
苦しみの中でも信念を貫いた晋作の姿に、現代の私たちは“生き方の本質”を見出せるかもしれません。
髷(まげ)を自ら切った「破戒の志士」だった?
■ 髷(まげ)とは何か?――武士の“身分証明”だった
江戸時代の日本において、「髷を結うこと」=武士である証でした。
前髪を剃って後ろ髪を結い上げる「丁髷(ちょんまげ)」は、武士階級を象徴するスタイルであり、町人や農民がこれを結うことは基本的に許されていませんでした。
つまり、髷を切る=武士の身分を捨てるという意味を持っていたのです。
それは一種の“破戒”であり、“自ら武士階級を否定する”行為とも受け取られました。
■ 高杉晋作、まさかの断髪――その驚きの理由とは
高杉晋作が髷を切ったのは、奇兵隊の創設にあたっての出来事でした。
奇兵隊は、武士に限らず、町人・農民・神職などあらゆる階層の人々が参加できる“身分を超えた軍事組織”。それは当時としては非常に革新的な思想でした。
そんな中、「士農工商」の身分制を打ち破るため、晋作は自らの髷を切ることで“平民と同じ立場に立つ”姿勢を明確に示したのです。
この行動により、彼は指導者としての絶対的な信頼と共感を得ることになりました。
「自分は偉いから上に立つのではない。共に戦う仲間だから、同じ目線でいるのだ」――
その覚悟が、言葉ではなく、見た目にまで表れた瞬間でした。
■ 保守派からの批判と、それを上回る“カリスマ性”
当然ながら、長州藩の保守派や藩の上層部からは、「髷を切るとは何事か!」という非難の声も上がりました。
しかし、晋作はそうした批判に怯むことなく、次々と実行力をもって行動し、民兵からの信頼を獲得していきます。
彼の行動は、単なる反骨精神ではありません。
“武士の身分に甘んじない”という、時代の殻を破るリーダー像の体現でもありました。
■ 「破戒の志士」=新しい時代を切り開く象徴
晋作の断髪は、ただ髪を切ったという話ではありません。
それは、幕末という身分制度の揺らぐ時代に、武士自身がその制度を打破する“象徴的な行動”だったのです。
この姿勢は、のちの「脱藩」や「攘夷」「倒幕」など、枠を超えた行動をとる志士たちにも多大な影響を与えました。
一部の歴史学者からは、晋作の断髪こそが“精神的な明治維新のはじまり”だったと評価する声もあります。
■ まとめ:命を賭して「同じ目線」に立った男
自らの身分も誇りもかなぐり捨てて、人民と同じ目線に立つ――
高杉晋作の断髪は、まさに命を懸けた“メッセージ”でした。
形式や体裁を守ることよりも、「何を実現するか」に重きを置いた生き方。
その姿勢が、彼を“破戒の志士”ではなく、“革命の旗手”として後世に伝える大きな理由なのです。
■自毛植毛クリニック
アルモ形成クリニックは2023年9月にオープンした自毛植毛をメインとしたクリニックとなります。
詩人としての才能も一流だった?
■ 幕末屈指の“文武両道”の志士
高杉晋作と聞くと、奇兵隊の創設や功山寺挙兵など、破天荒で大胆な行動家というイメージが強くあります。
しかしその一方で、彼は和歌・漢詩・書においても非凡な才能を発揮した“詩人”でもありました。
晋作は幼少期から漢籍を学び、吉田松陰の松下村塾では思想と共に文才も鍛えられました。松陰自身が文学に通じた人物であり、晋作の文才を非常に高く評価していたと伝わります。
また、晋作は人の心を動かす言葉の力を重視しており、演説や檄文にも詩的な表現を織り交ぜていたことが知られています。彼の発する言葉には、ただの理論ではない、“情熱”と“美意識”が込められていたのです。
■ 有名な一句「おもしろき こともなき世を おもしろく」
晋作の詩の中で、最も広く知られているのがこの一句:
「おもしろき こともなき世を おもしろく」
この句は、病床で詠んだとされ、死を目前にしながらも、
「たとえつまらぬ世の中であっても、自分の力で面白く変えてやる」
という前向きな精神を表現したものとされています。
一説には、これは実は上の句だけで、下の句は親交のあった尼僧・野村望東尼が
「すみなすものは 心なりけり」
と続けたとも言われていますが、いずれにしてもこの句は晋作の思想と人生観の凝縮された言葉として今も愛され続けています。
■ 革命と詩は矛盾しない――心を動かす力としての詩
晋作が詩や言葉を愛したのは、単なる趣味ではありません。
革命の手段として、詩を「心を動かす武器」として用いたのです。
彼の残した詩には、自由を求める熱情、儚くも燃え尽きる命への覚悟、仲間への慈しみ、そして死への諦観といった、時代を超えて共感される人間的な感情が込められています。
また、敵味方を問わず人を魅了する言葉の使い手として、晋作は同時代の志士たちにも強い影響を与えました。
■ 書の達人でもあった晋作
高杉晋作は、筆跡にも優れており、書の作品もいくつか現存しています。
「快筆乱麻」と称されるほどの筆さばきで、流麗かつ力強い書体を残しました。
彼の書は、まるでそのまま声になって響いてくるような“詩的な書”とも言われ、
見る者に強いインパクトを与えるものでした。
■ まとめ:剣と筆、両方を手にした稀有な革命家
高杉晋作は、ただの剣と策の人ではありませんでした。
言葉を操る才能と、魂を込めた詩情を併せ持つ、“武と文”の融合体。
その詩や書は、今なお多くの人々の心を打ち、
激動の時代を生きた若者の“内なる声”を私たちに語りかけてくれます。
まとめ
高杉晋作といえば、幕末の長州藩を揺るがす奇兵隊の創設者であり、維新回天の立役者として名を馳せる人物。
しかし、その鮮烈な生涯の裏には、私たちがあまり知らない“人間らしい素顔”が隠されていました。
恋に生き、遊女「おうの」と心を通わせた「長州一のモテ男」。
命を削るように活動を続ける中、病と闘いながらもアヘンで咳を抑えてまで志を貫いた覚悟。
封建社会に真っ向から挑むべく、自らの髷を切って庶民と同じ立場に立った破戒の志士としての決意。
そして、剣や言葉で人の心を動かすだけでなく、詩や書でもその魂を表現し続けた文化人としての一面――
そのどれもが、ただの“維新の英雄”では終わらない、
「信念と情熱をもって生きた一人の人間・高杉晋作」の姿を、今に伝えてくれます。
型破りな行動の裏には、理想への強い思いと、人間味あふれる優しさがあった――
そんな彼の本当の魅力に、今こそ目を向けてみてはいかがでしょうか。
■鮮度長持ち!食材をいつでも新鮮に【FOOD SEALER】
・使い切れない食材を真空保存で鮮度長持ちさせる ・カレーやシチューなどのお料理も真空保存。いつでも作りたての美味しさを
■離れていても、いつでも一緒。【新型Furboドッグカメラ – 360°ビュー】
Furbo(ファーボ)は、ドッグオーナー、獣医、ドッグトレーナーなど 5,000人以上の愛犬家の声を反映させ、世界133ヶ国100万人以上の愛犬家が愛用している愛犬専用に設計されたドッグカメラです。
■国内トップクラスの実績!防災セットメーカーLA・PITA直営サイト【アットレスキュー】
あの楽天市場において、防災セットで初めて総合1位を獲得した超人気防災セット「SHELTERシリーズ」を始め、 国内実績トップクラスの防災セットメーカーLA・PITAが開発した防災セットがズラリ!
■グリーンラビット
可愛らしいうさぎやネコのデザインが施されたアパレルコレクション。メンズ・レディースともに楽しめる、シンプルながらも遊び心のあるデザインが魅力です。カジュアルなTシャツやスウェットから、上品なシャツやジャケットまで幅広く展開。