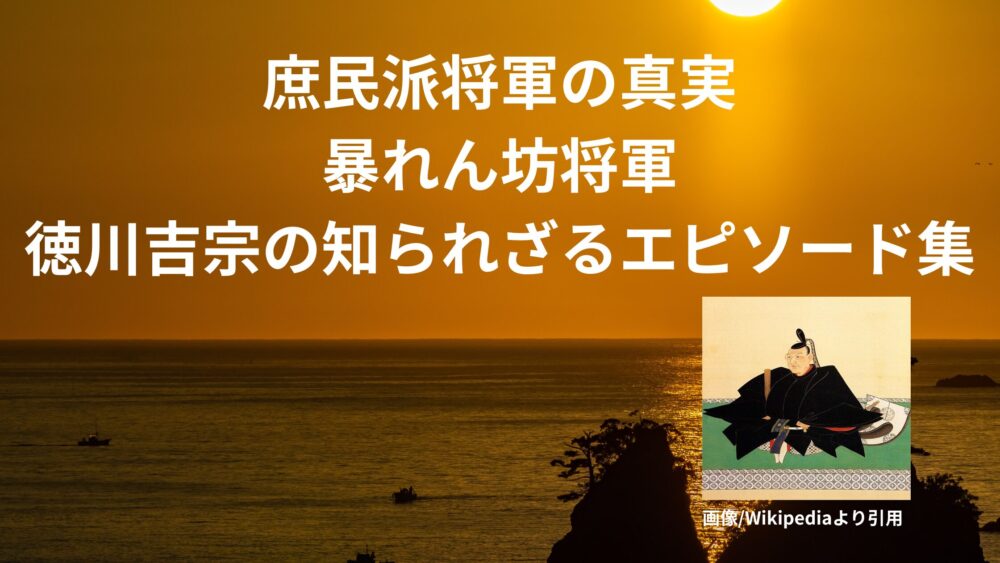徳川吉宗で最もよく知られるのは、享保17年(1732年)に起こった「享保の大飢饉」の際、サツマイモを救荒作物として全国に普及させたエピソードです。冷夏と稲の害虫被害で米が不作となった西日本で、飢饉による餓死者が1万人以上にのぼるなか、吉宗は長崎藩からの報告で薩摩(現在の鹿児島)ではサツマイモで飢饉を乗り切ったことを知りました。そこで儒学者・青木昆陽(1698–1769)にサツマイモの栽培研究を命じ、江戸小石川や吹上御苑での試作を経て、関東一円、さらには全国に栽培を奨励。結果的に飢饉の被害を大幅に軽減し、以来「芋代官」「甘藷先生」と呼ばれるほど庶民の命を救ったと伝えられます。
幼少期に“捨て子”同然の扱いを受けた説
幼少期に吉宗(当時は頼方〈よりかた〉と名乗る)は、父・徳川光貞が60歳を超えて藩主となったことから「年老いた父の子は元気に育たない」という迷信を避けるため、一度和歌山城内の松の木の根元に“捨てられた”と伝わります。これは完全な見捨てではなく、一種の厄祓い儀礼として行われた儀式で、通りかかった家老・加納政直が「たまたま拾った」という体裁を取るものでした。
その後、政直の屋敷で乳母・おむつ(幼名は新之助)の手で大切に育てられ、5歳になるまで加納家で過ごします。ちょうどその頃、次兄・次郎吉(じろきち)が病死したため、頼方は新之助から改名して改めて江戸の紀州藩邸へ移住。幼少期は手に負えないほどの暴れん坊ぶりを見せましたが、この「捨て子」儀礼体験が、後の庶民重視の政治感覚や、弱者への共感を育む原点とも言われています。
■横濱みなと珈琲|ベトナム産コーヒー豆
日本とベトナムの魅力が詰まったとっておきのコーヒーを、横濱から皆さまのもとへお届けします。

幼い頃、自前の“行列”を組んで大名行列に対抗した
幼少期、紀州藩邸の物見所から久留米22万石・有馬玄蕃守則維の大名行列を見た頼方(後の吉宗)は、「かばかりの人ともならまほしき事ぞ(これほど多くの人付きがいる大人物になりたいものだ)」とつぶやきました。その後、頼方は友人や小姓を数名集め、自作の“行列”を組むことを思い立ちます。端材の布で小さな幟(のぼり)を仕立て、小太鼓を借り、さらに子ども用の駕籠や玩具の弓矢を揃えて隊列を構成。藩邸前や城下町を、自前の「大名行列」に匹敵するスケールで練り歩き、見物の庶民を驚かせつつも大いに沸かせたと伝えられます。このエピソードは、幼くして周囲を巻き込む行動力と自らの願望を形にする才気を示すものとして語り継がれています。
紀州藩主時代、夫婦喧嘩に学んで“訴訟箱”を設置
紀州藩主となる以前、和歌山城下をお忍びで歩いていた吉宗(当時は頼方)は、ある夫婦の激しい口論を目撃しました。咄嗟に仲裁に入ったものの、喧嘩を止めようとする隣人に対し「殿様でもない人の言うことなど聞けるか!」と罵声を浴びせる二人の姿を見て、身分を超えて“殿の声”を届けねば意味がないことを痛感したといいます。
藩主就任後、この経験を忘れなかった吉宗は、庶民の声を直接政治に活かすため、和歌山城大手門前に「訴訟箱」を設置しました。これは後の江戸城・目安箱の原型ともなるもので、訴訟箱に投書された意見や苦情を藩主自ら—or 場合によっては側近を通じて—受け取り、迅速に対応させる仕組みを作り上げています。
訴訟箱の設置によって、これまで藩士や役人を介さなければ届かなかった民意が直に藩政に反映されるようになり、吉宗の「質素倹約」や財政再建策が庶民支持を得て円滑に進められた背景には、このコミュニケーションの仕組みが大きく寄与したとされています。
■ビアキューブ直販ストア|永久に溶けない氷『ビアキューブ』
水の氷のように冷却するのではなく、ビールのように元々冷たくしている飲み物を薄めずに、
飲み終わりまで冷えた状態をキープする保冷アイテムです。

江戸で“お忍び”の町歩きを頻繁に行った
江戸市中を将軍自らが気ままに徘徊したという“暴れん坊将軍”的な逸話はほぼ創作に近く、実際の吉宗は城外の鷹狩りを「お忍び」と称して私的に行うことはあっても、市中をぶらぶら歩くことはほとんどありませんでした。鷹狩りは公的行事ではなく私的な狩猟だったため、「お忍び」と呼んで段取りを簡略化し、家臣への負担を減らす配慮がなされていたといいます。
代わりに吉宗が重用したのが、将軍直属の隠密組織「御庭番」です。御庭番は、命を受けて江戸市中や大名領内に身分を隠して潜入し、その動静や風聞を将軍に報告する諜報機関として機能しました。吉宗は自ら街を歩くよりも、情報収集は信頼する御庭番に一任し、彼らを通じて庶民の暮らしぶりや諸藩の動きに即応しました。
さらに御庭番の隠密行動は、呉服店を連絡所として利用し、赴任前に店内で予め用意された衣装に着替えてまったく別人の姿に変装するといった巧妙なものでした。こうして都心や郊外へ派遣された御庭番は、身分を隠しつつ情報を収集し、報告書(風聞書)にまとめて幕政に反映させました。このように、吉宗の「お忍び町歩き」はドラマ的演出に過ぎず、実際は御庭番と私的な狩猟で幕政の情報網を構築していたのです。
まとめ
徳川吉宗(1684–1751)は、紀州藩主の四男として生まれ、1716年に江戸幕府第八代将軍となりました。享保の改革と呼ばれる一連の政策では、財政再建のための倹約令・貨幣改鋳を断行し、農業振興策としてサツマイモの普及を推進しました。また、庶民の声を直接聴く仕組み(目安箱の原型)を整備し、学問と文教にも力を注いだことで、幕府の統治基盤を強化。鷹狩りを「お忍び」と称して私的に行う一方、御庭番を駆使して情報網を張り巡らせるなど、柔軟かつ実務的なリーダーシップを発揮しました。その結果、享保期には比較的安定した治世を実現し、後世に「改革者将軍」として高く評価されています。
■表参道倶楽部|「30代40代50代の婚活をサポート」結婚相談所
結婚を真剣に考える初婚、再婚、30代、40代、50代の婚活をサポートいたします。
安心・安全!結婚によりそってきたウエディングスペシャリスト、結婚カウンセラーから生まれた婚活サービス・結婚相談所です。

■LiMEジム|パーソナルジム
都内を中心に30店舗以上を展開する「パーソナルトレーニングジムLiME」
キツくない運動でゆるいトレーニングで痩せるを実現します。

■らでぃっしゅぼーや|おためしセット
らでぃっしゅぼーやは、カラダと環境にもやさしい食材宅配サービスです。

■グリーンラビット
可愛らしいうさぎやネコのデザインが施されたアパレルコレクション。メンズ・レディースともに楽しめる、シンプルながらも遊び心のあるデザインが魅力です。カジュアルなTシャツやスウェットから、上品なシャツやジャケットまで幅広く展開。