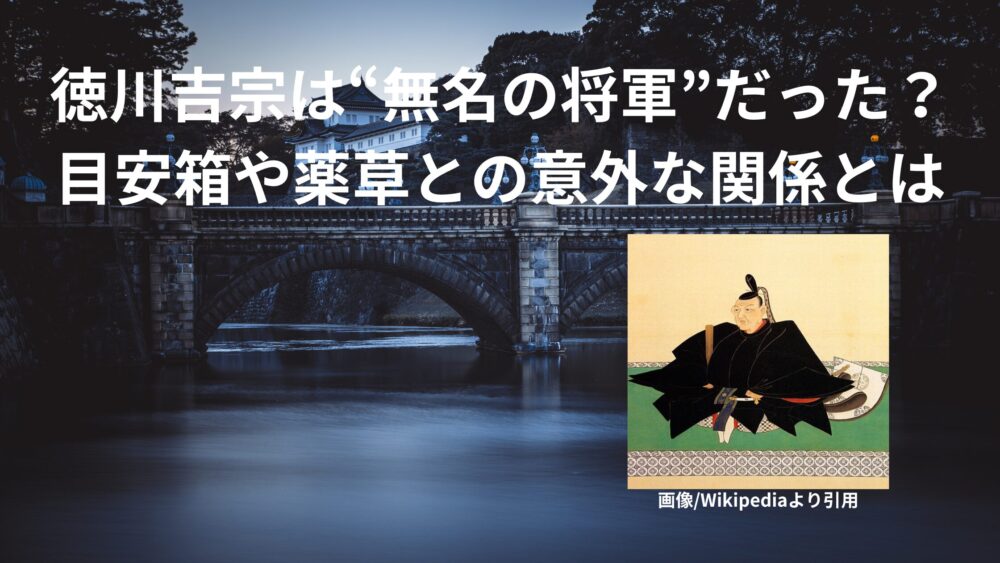✅ 「享保の改革」で幕府を立て直した名将軍
徳川吉宗は、8代将軍として有名な「享保の改革(きょうほうのかいかく)」を主導し、財政難に陥っていた江戸幕府を立て直した名君として知られています。
この改革では、
- 倹約令の徹底(将軍自ら質素な生活を実践)
- 年貢の引き上げと検地の強化
- 目安箱の設置による民意の吸い上げ
- 小石川養生所の設立など福祉政策
- 公事方御定書の制定による法の整備
といった、多岐にわたる施策が打ち出され、江戸幕府中期の安定化に大きく貢献しました。
吉宗の政治は「質実剛健」と評され、後世には「米将軍(こめしょうぐん)」と称えられるほど、庶民の暮らしに寄り添った実務派リーダーとして広く知られています。
将軍就任前は“無名の大名”だった?
〜紀州藩主から将軍へ、異例の出世劇〜
徳川吉宗(1684–1751)は、江戸幕府8代将軍として「享保の改革」を行った名君として知られていますが、実は将軍に就任するまではほとんど無名の存在でした。
■ 紀州藩主だった吉宗
吉宗は、徳川家の三大御三家のひとつ紀州徳川家の出身で、紀伊藩(現在の和歌山県)を治めていました。
しかし当時の紀州藩は財政難に悩まされ、吉宗は若くしてその再建に奔走。倹約や合理化を進めたことで藩内では評価されていたものの、幕府内では目立った功績や政治的な発言力は皆無だったのです。
■ なぜ無名の吉宗が将軍になれたのか?
これは、7代将軍・徳川家継がわずか8歳で死去し、しかも後継がいなかったという“空白”の事情によります。
当時の幕閣たちは、次の将軍として
- 徳川宗家の血筋に近い者
- 徳川家に忠実で実績のある者
- 将軍職にふさわしい人格者
という基準で人選を行い、そこで白羽の矢が立ったのが紀州徳川家の吉宗でした。
■ 幕府内でも驚きの声があがった?
吉宗は当時まだ30代後半。政治の中枢にいた経験もなく、江戸城の役人たちですら「誰だ?」という反応だったと伝えられています。まさに“無名からの大抜擢”。
それだけに、将軍就任後の「享保の改革」の成功は、彼の実力を証明する大きな出来事となったのです。
■ 「中興の英主」と称されたゆえん
無名からスタートし、民のための政治を断行し、財政の立て直しに成功した吉宗は、後に「中興の祖(ちゅうこうのそ)」とも呼ばれました。
徳川将軍家の歴史の中でも、“地味”な出自から“名君”へと上り詰めた数少ない人物です。
■創業89年・京都の伝統の味を召し上がってみませんか?
看板商品の【しば漬け風味おらがむら漬】は年間40万個以上を売り上げる不動の人気商品です。 初代ニシダや店主辻村安衛門の手によって、京都、洛北大原に伝わるしば漬を参考に、本来茄子が主であったも のを胡瓜に変え、独自の製法にて『おらがむら漬』は作られました。
「目安箱」は庶民からの“告発”も想定していた?
〜意見箱に隠された“監視システム”の側面〜
徳川吉宗といえば、「目安箱(めやすばこ)」の設置が代表的な政策のひとつです。享保の改革の一環として、民の声を政治に反映する革新的な制度として評価されていますが、その目的は単なる“ご意見募集”ではありませんでした。
実はそこには、庶民による“役人告発”の手段としての側面が強く含まれていたのです。
■ 江戸城前に設置された「目安箱」
享保6年(1721年)、吉宗は江戸城の評定所門前に「目安箱」を設置しました。
当時、一般の庶民が将軍や幕府に直接意見を届ける手段は皆無に等しく、この制度は身分を問わず、誰でも投書可能という点で非常に画期的でした。
■ 名前不要、内容自由。だから“内部告発”が可能に
目安箱に入れる投書は、匿名でも可。つまり、名乗る必要がなく、内容も自由。
これにより、普段なら口に出せないような、
- 役人による賄賂の要求
- 村役人の不正な年貢徴収
- 地方代官の横暴な支配
といった、“内部告発”ができる場としても機能したのです。
■ 実際に処罰された役人も多数いた
目安箱を通じて届いた情報は、幕府の役人たちによって調査され、実際に処罰された官吏や役人も多数記録されています。
吉宗自身がこの制度を「庶民の声を聞く」と同時に、「幕府内部の腐敗を正すツール」と位置づけていた証です。
■ 目安箱から誕生した画期的な政策も
この制度によって生まれた改革例として有名なのが、
- 小石川養生所(無料の医療施設)の設立
- 火消し制度の整備
- 貧民救済策の強化
などがあり、「実行力のある制度」として庶民からも支持されました。
■ 現代でいう“行政通報制度”の先駆け?
目安箱は、現代でいうところの「内部通報制度」や「市民オンブズマン制度」にも通じるものであり、江戸時代にあって非常に先進的な統治スタイルだったといえます。
吉宗の狙いは、「庶民からの信頼」だけでなく、「役人を上からも下からも監視する仕組み」をつくることだったのです。
実は「倹約家」ではなく“質素好き”だった?
〜政策ではなく“性格”からにじみ出たシンプルライフ〜
徳川吉宗といえば、享保の改革の中で「質素倹約」を掲げたことで知られます。将軍自ら無駄を省き、幕府や諸藩、町民にまで節約を促したことで、「倹約家の将軍」というイメージが定着しています。
しかし近年の研究では、吉宗のこのスタイルは単なる財政政策ではなく、彼の“個人的嗜好”に根ざしたものであったと指摘されています。
■ 藩主時代から続く“徹底した質素生活”
吉宗は将軍になる前、紀州藩主としてすでに質素な生活を実践していました。
例えば──
- 着物には継ぎがあり、染め直して何度も使用
- 料理は一汁一菜が基本。将軍になっても変わらず
- 道具や家具も修繕しながら長く使う
というように、節約というより“ムダが嫌い”という性格がにじみ出ています。これは、紀州藩の財政再建に真剣に取り組む中で染み付いた生活感覚でもありました。
■ 「贅沢禁止」は他人への強制ではなかった?
享保の改革では、幕臣や町人に対しても贅沢を控えるよう命じられましたが、吉宗自身が実践していたからこそ説得力があったのです。
つまり、「自分は質素にしてるけど、周りは贅沢していい」とはせず、まず自らが模範を示してから他人にも倹約を求めました。
このため、彼の倹約政策は“厳しい取り締まり”というより、「上に立つ者が身を律する」という、道徳的・倫理的影響力を重視したものだったといえるでしょう。
■ 金は「民のため」に使うという信念
とはいえ、吉宗は必要な投資には決してケチらない人物でした。
- 医療施設(小石川養生所)の設立
- 法令整備(公事方御定書)による司法の明文化
- 農業奨励や飢饉対策への支出
など、「民を救う・社会を安定させる」ための支出には躊躇がなく、むしろ積極的でした。
これは、“倹約家”というより、お金をかけるべきところと節約すべきところを明確に分けていた、理知的な支配者だったことを示しています。
■ 「節約」と「人格」が結びついた政治スタイル
吉宗の質素さは単なる政策ではなく、一人の人間としての生き方・美学だったとも言えます。だからこそ、人々の心を動かし、「中興の英主」と称えられたのでしょう。
■ふるさと納税を始めるなら【au PAY ふるさと納税】
KDDIとau コマース&ライフが共同運営するふるさと納税ポータルです。 Ponta ポイントが使える&貯まってお得! お肉や海鮮などグルメを筆頭に、人気自治体の返礼品を多数取り揃えています。
自ら薬草を育て、医療の発展に尽くしていた?
〜“将軍=薬草マニア”? 江戸の福祉政策の先駆者〜
享保の改革を進めた徳川吉宗は、経済や農政だけでなく、医療制度の整備にも強い関心を持っていました。特に注目されるのが、「薬草栽培」と「庶民医療」の推進です。
実は吉宗自身が、薬草園の設立を命じたり、自ら薬草栽培に関わる指示を出していたという記録も残っています。
■ 「小石川養生所」を開設し、庶民を無償で治療
享保7年(1722年)、吉宗は「小石川養生所(こいしかわようじょうしょ)」という医療施設を開設。
これは、経済的に困窮する庶民のために無料で診察・治療を行うという、日本で初めての“公的医療機関”のような存在でした。
場所は現在の東京都文京区小石川。施設の運営には幕府が直接関与し、当時の医師や漢方家が診療を担当。
医療というものを「富裕層のための特権」ではなく、「庶民の健康を守る社会的インフラ」としてとらえた先駆的な取り組みでした。
■ 小石川養生所には「薬園」も併設
小石川養生所には、吉宗の命により「御薬園(おやくえん)」が併設されていました。
ここでは、漢方薬に使う薬草の試験栽培・研究が行われ、国内で採取しにくい薬草を育てる試みも行われました。
吉宗は、
- 日本各地の薬草情報の収集
- 栽培方法の研究
- 将来的な薬草の自給体制の確立
に強い関心を持ち、薬草園の整備を国家事業として推進していたのです。
■ オランダ医学(蘭学)への理解もあった
吉宗は漢方医学だけでなく、西洋の医学にも一定の理解を示していました。
とくに、長崎の出島を通じて伝わってきたオランダの医学書(蘭書)に関心を持ち、翻訳を許可するようになります。
これにより、後に杉田玄白らが『解体新書』を編纂するなど、日本の近代医学の礎が築かれていくのです。吉宗の開明的な姿勢が、時代を超えて影響を与えました。
■ 「薬で人を救う」ことを政治に取り込んだリーダー
当時の将軍が医療や薬草にここまで深く関わった例は他になく、吉宗は日本史上でも異色の“医療リーダー”といえる存在です。
単なる倹約家でもなく、支配者でもなく、「人の健康と命を守る」ことに強い関心を抱いた姿勢は、江戸の福祉政策の先駆けとも言えるでしょう。
まとめ
徳川吉宗といえば、「享保の改革」や「質素倹約」で知られる名将軍ですが、その背景にはあまり知られていない多くの魅力が隠れています。
将軍就任前は幕府内でほとんど知られていない“無名の大名”だった彼は、庶民の声を直接聞くための「目安箱」を設け、不正を告発できる仕組みまで整えました。
また、倹約を押し付ける支配者ではなく、自ら質素な生活を貫いた誠実な人柄が人々に信頼を与え、強い政治的求心力となっていきます。
さらに、自ら薬草園を整備し、貧しい人々に無料の医療を提供するなど、江戸時代にしては極めて先進的な福祉政策も打ち出しました。
これらのエピソードから浮かび上がるのは、「民を思い、実行し、模範を示した将軍像」。
徳川吉宗は、ただの改革者ではなく、“人間性”と“実行力”を併せ持った希有な名君だったといえるでしょう。
■鮮度長持ち!食材をいつでも新鮮に【FOOD SEALER】
ドライフードから、少し水気のある食材までカバーできる真空パック機 キャニスターもついているので、液体系のお料理の保存にも使えます。
■補聴器とは違う、全く新しい会話サポートイヤホン【Olive Air】
補聴器とは違う、全く新しい会話サポートイヤホン「オリーブエアー」 より進化した音声処理技術とパワフルな音量で、どんな環境でも会話を快適にサポート。
■離れていても、いつでも一緒。【新型Furboドッグカメラ – 360°ビュー】
Furbo(ファーボ)は、ドッグオーナー、獣医、ドッグトレーナーなど 5,000人以上の愛犬家の声を反映させ、世界133ヶ国100万人以上の愛犬家が愛用している愛犬専用に設計されたドッグカメラです
■グリーンラビット
可愛らしいうさぎやネコのデザインが施されたアパレルコレクション。メンズ・レディースともに楽しめる、シンプルながらも遊び心のあるデザインが魅力です。カジュアルなTシャツやスウェットから、上品なシャツやジャケットまで幅広く展開。