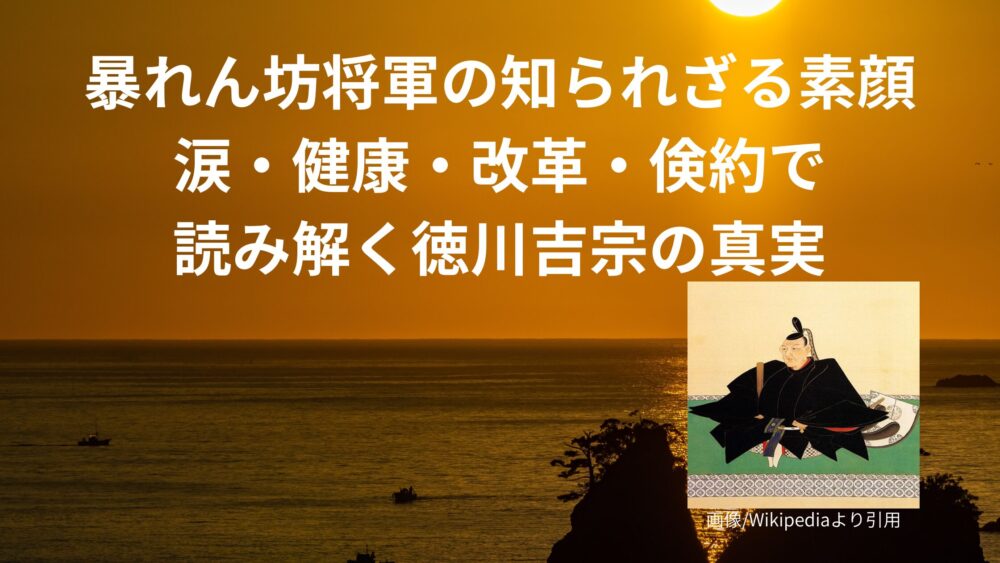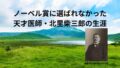🌾【有名な話】「米将軍」と呼ばれた徳川吉宗 ― 米価を守った庶民思いの政策
吉宗は、将軍に就任したころ、幕府の財政が非常に厳しい状態にあることを知りました。
物価が上がり、特に米の値段が乱高下していたため、庶民の生活が苦しくなっていたのです。
そこで吉宗は、米の値段を安定させるためにさまざまな政策を打ち出しました。
その中でも有名なのが「米の備蓄制度(囲米)」です。
これは、豊作の年には米を蓄えておき、凶作の年に放出することで、米の値段が急に上がったり下がったりしないようにする仕組みでした。
また、農村を再生させるために新田開発にも力を入れました。
荒れ地や湿地を耕して米を増やし、庶民が飢えないようにしたのです。
こうした政策によって、江戸の町には米が安定的に出回り、庶民から「米将軍(こめしょうぐん)」と呼ばれるようになりました。
涙の将軍・徳川吉宗――“暴れん坊”の裏に隠された人情の決断
徳川吉宗は、一般的には「暴れん坊将軍」として知られ、厳格で決断力のある将軍というイメージが強い人物です。
しかし、その内面には深い“人情”を持った一面がありました。
ある日、江戸で一人の浪人が罪を犯して捕らえられました。
浪人は盗みの罪で裁かれることになり、重い処罰が下されようとしていました。
ところが、詳しく調べてみると、彼が盗んだのは金品ではなく、
飢えた子どもに与えるための、ほんの少しの食べ物だったのです。
法に照らせば、盗みは盗み。
将軍として法を曲げることはできません。
しかし、吉宗はこの浪人の事情を知り、深く胸を痛めました。
「この男を救えば、法の信頼が失われる。だが、このままでは人の情が死んでしまう」
そう悩みながらも、吉宗は涙をこらえて処罰を執行するよう命じます。
その夜、吉宗は静かに涙を流したと伝えられています。
そして、側近に密かに命じました。
「この浪人の子どもを保護し、きちんと育ててやれ」
この出来事は、法と情のはざまで苦しむ吉宗の“人間らしさ”を象徴する話として伝わっています。
彼は冷酷な支配者ではなく、「民のためにこそ厳しく、そして優しくあろうとした将軍」でした。
こうした逸話から、吉宗は「涙の将軍」と呼ばれることもあります。
その判断には、単なる感情ではなく、「法を守ることで人を守る」という信念があったのです。
■駅市 薩摩川内|鹿児島県の特産品
美味しい県 鹿児島県。
黒豚や薩摩揚げ、安納芋を使用したスイーツなど盛りだくさん。
ここでしか手に入らない鹿児島県の特産品をお取り寄せ。

江戸にサウナ文化を広めた!? 徳川吉宗の驚くべき健康法
徳川吉宗は、「享保の改革」で知られる8代将軍ですが、実は政治だけでなく健康管理にも非常にストイックだった人物です。現代でいえば“ウェルネス将軍”や“サウナ好きのリーダー”といっても過言ではありません。
🐎 朝のルーティンは「運動+質素な朝食」
吉宗は毎朝、日の出とともに起き、まずは馬に乗って江戸城の外を走りました。
「体を鍛えることが心を整える第一歩」と考えていたからです。
食事も驚くほどシンプルで、白米ではなく玄米を好み、おかずは味噌汁や野菜の煮物など、栄養を重視した“粗食主義”でした。
当時、将軍といえば贅沢な食事を取るのが当たり前でしたが、
吉宗は「贅沢は体を弱らせる」と言い、余分な油や砂糖を控えていたといわれます。
♨️ 毎日の蒸し風呂――江戸の“サウナ王”
吉宗が特にこだわっていたのが蒸し風呂です。
今でいう「サウナ」に近いもので、木製の小屋に湯気を満たして体を温め、汗をたっぷり流していました。
吉宗はこの蒸し風呂を“毎日欠かさなかった”と伝えられています。
「汗をかくことで毒を出し、心身を清める」と信じていたのです。
この習慣はやがて江戸庶民にも広まり、風呂屋(現在の銭湯)がどんどん増えていきました。
「将軍が毎日風呂に入るなら、私たちも健康になろう!」という考えが、江戸中に“風呂文化”を広めるきっかけになったのです。
🩺 予防医学の先駆け――「体を守る政治」
当時はまだ医療が発展しておらず、病気になれば命を落とす時代でした。
そんな中で吉宗は、「病気になる前に体を整えることが大切だ」と考えていました。
これはまさに予防医学の考え方です。
彼は将軍でありながらも、「健康こそ政治の土台。民の健康が国の力を作る」と語っていたと伝わります。
また、健康を支えるために薬草の研究や医師の育成にも関心を持ち、
幕府に医療制度の整備を命じました。
🌿 健康が作った“安定した政治”
規則正しい生活と清潔な習慣を重んじた吉宗の考え方は、江戸の社会に「健康は文化である」という価値観を根づかせました。
その結果、風呂文化や清潔意識が広まり、江戸は世界的にも衛生的な都市へと成長したのです。
庶民の声が江戸を変えた!“目安箱”を作った徳川吉宗の改革
徳川吉宗といえば、「享保の改革」で知られる江戸幕府8代将軍です。
中でも最も象徴的な改革が、庶民が直接意見を伝えられる制度――「目安箱(めやすばこ)」の設置でした。
🏯 “民の声を聞く”前代未聞の試み
1721年(享保6年)、吉宗は江戸城の門前に「目安箱」を設置しました。
目的は、庶民からの意見や要望を直接集めること。
つまり、将軍が民の声を“自分の耳”で聞こうとしたのです。
当時の日本では、身分の低い庶民が政治に意見を言うことなどありえませんでした。
しかし吉宗はこう考えたのです。
「政治を動かすのは、法でも金でもない。人々の暮らしの声だ。」
📩 最初は誰も入れなかった!?
ところが、設置当初は誰も手紙を入れませんでした。
「どうせ将軍が読むはずがない」「意見を出したら処罰されるかもしれない」――
庶民たちはそう思っていたのです。
しかし吉宗は、本当に目安箱を開けて読んでいました。
しかも、一枚一枚に目を通し、内容を精査。
その中から、採用できる意見を政策に反映させたのです。
🔥 江戸を救った“町火消し”の誕生
投書の中には、「火事が多くて困っている。町火消しを作ってほしい」という意見がありました。
江戸は木造建築が多く、火災が頻発していたため、この要望はとても切実なものでした。
吉宗はその意見を採用し、町人による消防組織「町火消し(いろは四十七組)」を創設。
この制度により、江戸の火災被害は大幅に減少し、町人たちの間に「自分たちの町は自分たちで守る」という誇りが生まれました。
🩺 ほかにも広がった改革
目安箱から生まれた意見は、火消しだけではありません。
「医師の教育制度を整えてほしい」
「貧しい人にも薬を手に入れられるようにしてほしい」
といった声もあり、これが後の小石川養生所(貧民のための無料診療所)の設立につながりました。
🗳️ 民主主義の“はじまり”とも言える制度
吉宗の「目安箱」は、今でいえば“国民の意見箱”のような存在でした。
庶民が社会に意見を届け、それが政策に反映される――
これは日本史上初の「民意を政治に反映させた制度」だったのです。
吉宗は、権威よりも実際の暮らしを重視する政治を目指しました。
だからこそ、彼の政治は庶民の信頼を集め、「暴れん坊将軍」ではなく“民の将軍”として尊敬されるようになったのです。
■防犯-ダイレクト|防犯カメラや監視カメラの商品
防犯-ダイレクトは、防犯カメラや監視カメラの通販専門店で、業界32年の経験と信頼を誇ります。高品質な防犯カメラや関連機器を幅広く取り扱い、3年保証や迅速な発送、領収書発行などのサービスを提供しています。

爪楊枝1本まで節約!? 倹約将軍・徳川吉宗が目指した“民のための政治”
徳川吉宗は、江戸幕府8代将軍として「享保の改革」を行い、幕府財政を立て直した人物として知られています。
彼の改革の根本にあったのは、「自分が率先して倹約すること」でした。
その徹底ぶりから、吉宗は「倹約将軍」と呼ばれるようになります。
🏯 華やかな江戸城を“質素な城”に変えた将軍
将軍の住まいである江戸城は、金箔の障子や贅沢な装飾で彩られていました。
しかし、吉宗は就任後すぐにこう命じます。
「金箔の障子は白紙に張り替えよ。無駄な装飾はいらぬ。」
さらに、庭の池に泳いでいた鯉を「無用の長物」として放流。
幕府の行事でも金銀の飾りを減らし、江戸城全体を“質素で清らかな空間”に改めました。
この姿勢は、家臣や庶民に「将軍が本気だ」と伝わり、倹約の空気が江戸中に広まっていきました。
🥢 「爪楊枝1本も無駄にするな」
吉宗の倹約精神を象徴する有名な話があります。
ある日、家臣が食後に使った爪楊枝をうっかり床に落とし、そのまま捨てようとしました。
それを見た吉宗はこう言ったといいます。
「一本の楊枝にも木を切る手間がある。無駄にしてはならぬ。」
この一言には、単なる節約だけでなく、
“物の命を大切にする”という深い思想が込められていました。
江戸時代は今のように大量生産の時代ではなく、すべてのものに人の手がかかっていました。
吉宗はそれを理解し、「ものを大事にする心」を政治の根本にしたのです。
💰 倹約の目的は“民の税を軽くするため”
吉宗の倹約は、自分のための節約ではありませんでした。
その目的は明確で、
「幕府の無駄を減らし、庶民の負担を減らすため」
だったのです。
当時の幕府は浪費が続き、財政が悪化していました。
吉宗はまず、自分たち支配層が贅沢をやめなければならないと考え、大名や役人にも質素倹約を命じました。
これにより、幕府の出費は大幅に削減され、財政再建の基盤が整っていきます。
この一連の改革が、後に有名な「享保の改革」として歴史に残るのです。
🧭 倹約が生んだ“信頼の政治”
吉宗は「倹約は恥ではない。誠実の証だ」と考えていました。
実際、彼の質素な暮らしぶりは庶民の間で評判になり、「自分たちと同じ目線で国を治めてくれる将軍」として多くの人々の信頼を集めました。
その姿勢は、単にお金を節約するだけでなく、「人の暮らしを守る政治」へとつながっていきました。
まとめ
徳川吉宗といえば、改革の象徴「享保の改革」や“暴れん坊将軍”の印象が強いですが、
その実像は、「民のために生きた名君」でした。
涙を流しながらも法を守り、人の命を思った「涙の将軍」。
毎日の運動と蒸し風呂で体を整え、健康を国づくりの基盤とした「ウェルネス将軍」。
庶民の声を聞くために目安箱を設け、政治を民とともに進めた「改革将軍」。
そして、爪楊枝1本を無駄にしない倹約精神で、幕府と庶民の暮らしを支えた「倹約将軍」。
これら4つの側面から見えるのは、権力者としての威厳よりも、一人の人間としての誠実さと情の深さです。
吉宗は「法」と「人情」の両立を目指し、「贅沢を減らして民の税を軽くする」「健康を守ることが政治」「庶民の声を聞くことが国を安定させる」――そんな考え方を実際の政策に変えた将軍でした。
だからこそ、彼の時代は江戸の安定期へとつながり、庶民の生活は少しずつ豊かになっていきます。
厳しさの中に優しさを持ち、理想を現実に変えた「民の将軍」――それが、徳川吉宗の本当の姿なのです。
■PRIMESHOP.JP通販サイト|健康的で美味しいイタリアの食材・調味料などの商品
primeshop.jpというイタリア食と健康ライフスタイルに関するブログで紹介した食材を中心として、
高級イタリアンレストランで使用される食材を紹介しています。

■マーケニスタ|Webマーケティング・動画制作・デザイン・DX・AI関連のオンラインサロン型の学習サービス
16カテゴリ600レッスン以上のコンテンツがあり、随時更新中。
月1回のオンライン勉強会、月1回のオンラインのワーク会など充実のサポート。

■必ずトレーナーがつくフィットネスクラブ「Forzaフィットネススタジオ」
パーソナルトレーナーが複数のお客様を同時に指導するセミパーソナルトレーニング方式を採用したフィットネスクラブです。
フィットネスクラブを利用する料金で、パーソナルトレーニングのサービスを受けることができます。