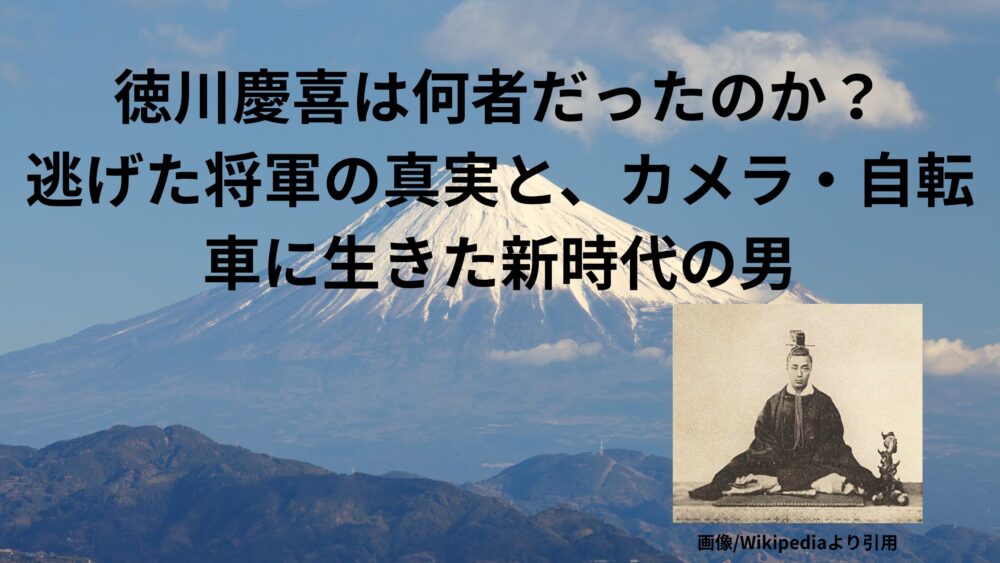🏯「大政奉還(たいせいほうかん)」の決断
1867年(慶応3年)、幕末の動乱が頂点に達したとき、徳川慶喜は“政権を朝廷に返す”という大胆な行動をとりました。
これが有名な「大政奉還」です。
表面上は「幕府が終わる」出来事でしたが、実際は“血を流さずに新しい時代へ移るため”の戦略的な判断でした。
慶喜は自らの手で徳川の時代を終わらせ、日本を内戦の悲劇から救おうとしたのです。
この決断により、日本は比較的平和に明治へ移行。
そのため、後の歴史家たちは慶喜を「戦わずして国を救った将軍」と評価しています。
徳川慶喜は“カメラオタク”!? 将軍がレンズを覗いた理由
📸幕末に現れた「写真好きの将軍」
最後の将軍・徳川慶喜(1837〜1913)は、政治家としてよりも、実は“趣味人”としての一面が非常に魅力的な人物でした。
その代表的な趣味が――「写真撮影」。
幕末の日本にカメラが伝わったのは、ペリー来航から間もない頃。
まだごく一部の知識人しか触れたことのない最先端の技術でした。
ところが慶喜は、その新しい文化にいち早く反応します。
将軍職を退いた後、静岡の屋敷に「写真室」を設け、自らカメラを操作して撮影・現像まで行っていたと伝わっています。
当時は“撮られる側”がほとんど。しかし慶喜は“撮る側”にまわり、被写体として家族や家臣を撮影していたのです。
🧠なぜ慶喜はカメラに夢中になったのか?
慶喜は幼少期から西洋文化に関心を持っていました。
フランス式軍制の導入、洋装の採用、外国語の学習など、「開明的な将軍」として知られています。
そんな慶喜にとって、写真は“時代を写す科学”でした。
筆や絵ではなく、光で真実を残すという発想に魅せられたのです。
当時のカメラは非常に扱いが難しく、露光時間も数十秒以上、現像にも化学的な知識が必要でした。
それを自ら手ほどきなしに研究し、使いこなした慶喜は、まさに“日本最初期のアマチュア写真家”と呼べる存在です。
🖼慶喜が撮った写真たち
現在も残る慶喜撮影の写真は、家族写真・庭園風景・狩猟場面など、どれも穏やかなものばかり。
そこには、かつて政治の頂点に立った男の影はなく、ひとりの趣味人としてのやさしい眼差しが映っています。
慶喜は晩年、「写真は、人の心を写すものだ」と語ったと伝わります。
その言葉の通り、彼の写真には“戦いではなく、平和を見つめる視線”がありました。
🌸時代を超えた「最後の将軍」の姿
徳川慶喜というと、“幕府を終わらせた男”の印象が強いですが、実際には“新しい時代を楽しんだ知的な紳士”でもありました。
カメラというレンズを通して見ていたのは、もはや封建の世ではなく、文明と個人の時代。
つまり慶喜は、
“最後の将軍”であると同時に、
“最初の近代日本人”でもあったのです。
■ReBALAN|フケ・かゆみに原因から対策!スカルプシャンプー&美容液トリートメント
繰り返すフケ・かゆみにフォーカスした、医薬部外品のスカルプシャンプー&美容液トリートメントのセット商品です。

“チャリ将軍”? 徳川慶喜、老後の趣味がハイカラすぎた
🏯天下人から“趣味人”へ
徳川慶喜(1837〜1913)は、江戸幕府最後の将軍。
激動の幕末を生き抜き、政権を朝廷に返す「大政奉還」を行ったことで知られています。
しかしその後、政治の表舞台を去った慶喜は、まるで別人のような人生を歩みました。
それは“趣味に生きる自由人”としての、穏やかでユーモアある日々でした。
🚴♂️自転車に夢中になった将軍
慶喜が特に熱中したのが、自転車。
明治時代、自転車はまだ日本では極めて珍しく、“外国人の高級玩具”というイメージが強いものでした。ところが慶喜は、静岡に移り住んだあとこの乗り物に夢中になります。
輸入されたばかりの高価な自転車を購入し、毎日のように屋敷周辺を走り回っていたと伝えられています。当時の人々は驚き、「将軍様がチャリに乗ってる!?」と話題に。
その姿から、彼は“チャリ将軍”とも呼ばれるようになったのです。
🌸進化を恐れない「文明開化の男」
慶喜の自転車好きは、単なる遊びではありませんでした。
彼は若い頃から西洋文化に強い関心を持ち、フランス式軍制の導入や洋装など、常に新しいものを柔軟に取り入れてきた人物です。その精神は明治になっても変わらず、
「時代が変わっても楽しむ心を忘れない」という生き方に表れていました。
自転車に乗る姿は、もはや“権力者”ではなく、文明開化を体現するひとりの紳士。
慶喜は、幕末と明治という全く異なる時代を、「戦う」のではなく「楽しむ」ことで超えていったのです。
🧘♂️静岡での穏やかな日々
晩年の慶喜は、自転車以外にも、狩り・写真・釣り・西洋料理など、多趣味な生活を送りました。
政治を離れ、家族や友人とともに笑いながら過ごす日々。
そこには、天下を背負った将軍の重圧はもうありません。
人々の記録によると、慶喜は静岡の街を走るとき、子どもたちに優しく声をかけ、周囲の人々にとっては“気さくな紳士”そのものだったそうです。
💬まとめ「時代の先を走った将軍」
徳川慶喜というと「幕府を終わらせた男」というイメージが強いですが、その晩年はむしろ「近代日本を最初に楽しんだ男」でした。彼は自転車を通じて“変わることを恐れない”という生き方を体現したのです。
最後の将軍にして、
最初のハイカラ紳士――。
徳川慶喜はまさに、“時代の先を走った将軍”でした。
“逃げた将軍”の真実 徳川慶喜が日本を救った一手
🏯「逃げた」と呼ばれた最後の将軍
徳川幕府15代将軍・徳川慶喜(1837〜1913)は、“江戸幕府を終わらせた男”として知られています。
慶喜が政権を朝廷に返した「大政奉還」は、まさに260年以上続いた武家政治の終焉でした。
しかし当時、多くの人々はこう言いました。「慶喜は責任を放棄した」「戦わずに逃げた」と。
その評価は長く続き、彼の名には“敗者の影”がつきまとってきました。
だが近年の研究では、この「逃げた将軍」という見方が誤りであることが明らかになっています。
実は慶喜の決断こそ、日本を“内戦の悲劇”から救った歴史的な一手だったのです。
🧭幕末、日本が二つに割れかけた時
1867年当時、幕府の力は急速に衰えていました。薩摩や長州といった倒幕派は武力で政権奪取を狙い、
全国は一触即発の状態。
慶喜はこの状況を冷静に分析していました。もし戦えば、日本全土が戦場になる――。
戊辰戦争のような悲劇が、さらに広がると考えたのです。
そのとき彼が選んだのが「大政奉還」。
つまり、自ら政権を返すことで“争いの理由そのもの”を消してしまうという前代未聞の決断でした。
🕊「戦わずして勝つ」政治的天才
この大政奉還により、表面上は幕府が終わりましたが、慶喜の狙いはもっと先にありました。
彼は「徳川家そのものを生き残らせる」ことを目的としていたのです。
政権を朝廷に返すことで、朝敵(反逆者)という汚名を避け、
徳川家が“体制の中に残る道”を確保しました。
その結果、後の明治政府でも徳川宗家は滅ぼされず、静岡藩として再出発することができたのです。
つまり、慶喜は“負けた将軍”ではなく、「戦わずして国を守り、家を守った将軍」。
まさに「戦国の知将」に匹敵する政治的判断をした人物でした。
🌸「逃げ」ではなく「未来を見た撤退」
大政奉還ののち、鳥羽・伏見の戦いで旧幕府軍が敗北すると、慶喜は大阪城を離れ、江戸へ退きます。
この行動も「逃げた」と批判されましたが、実際はさらなる流血を防ぐための冷静な撤退でした。
慶喜は戦の指揮を放棄することで、新政府軍の憎しみの矛先を自分一人に集中させ、
江戸の町を戦火から守ったのです。
その後、勝海舟と西郷隆盛の会談によって“江戸無血開城”が実現。東京は焼かれず、数十万人の命が救われました。
🕊まとめ:真の“逃げない将軍”
「戦わなかった将軍」としての徳川慶喜。
けれど本当は、誰よりも日本と民の未来を見据えていました。
戦えば滅び、退けば生きる――その境界を見極め、慶喜は“戦わない勇気”を選んだのです。
その判断があったからこそ、日本は近代国家として生まれ変わることができました。
「逃げた将軍」ではない。彼は、“戦わずして未来を救った将軍”だったのです。
■和牛天絹|A5等級ブランド和牛(飛騨牛)の商品
日本有数のブランド和牛「飛騨牛」を販売しております。
その飛騨牛の中でも、最も上質な肉質とされる「但馬血統」の和牛のみを使用しております。

将軍から趣味人へ 徳川慶喜が“写真と釣り”に生きた日々
🏯権力を捨てた将軍の静かな再出発
徳川慶喜(1837〜1913)は、江戸幕府最後の将軍。
政権を朝廷に返上した“大政奉還”で歴史に名を刻みました。
しかしその後、彼は一切の政治的活動を断ち、静岡に隠棲します。
この決断は、幕末を生きた多くの武士の中でも極めて異例。
権力の座を離れた慶喜は、「将軍」ではなく「一人の人間」としての人生を歩み始めたのです。
📸写真に魅せられた知識人
静岡での暮らしの中で、慶喜が熱中したのが「写真」でした。
明治初期、カメラはまだ高価で扱いも難しく、一般人には縁遠い存在。
しかし慶喜は、フランスから最新のカメラを取り寄せ、自らレンズを覗き、シャッターを切り、現像まで行いました。
彼が撮影した写真は、家族の姿や庭の風景、日常の一瞬。
将軍という肩書を脱ぎ捨て、穏やかな笑顔を見せるその構図には、「平凡な幸せを愛した男」の温かい視点が宿っています。慶喜はまさに“日本初期のアマチュア写真家”でした。
🎣自然と語らう「釣り人・慶喜」
もうひとつの趣味が「釣り」。
彼は庭に池を作り、魚を放し、自ら竿を垂れて一日を過ごすことを好みました。
釣り仲間を家に招き、笑いながら酒を酌み交わすことも多かったといいます。
その姿は、かつて天下を動かした将軍とは思えぬほど穏やかで、まるで一人の“風流人”のよう。
慶喜は魚を釣る時間を通して、失われた戦乱の時代とは真逆の「静けさ」を味わっていたのでしょう。
それは、激動の幕末を生きた彼がたどり着いた“心の平和”でした。
☕文明開化を楽しんだ近代的紳士
写真や釣りのほかにも、慶喜は西洋料理・ワイン・楽器など、新しい文化を柔軟に受け入れた人物でした。自ら洋服を着こなし、客人には洋風のもてなしをする――
そんな姿から、周囲の人々は「ハイカラ将軍」と呼んだといいます。
彼にとって新しい文化は、権力の象徴ではなく「人生を楽しむ手段」。
明治という新しい時代を、“憎む”のではなく“味わう”姿勢で受け入れたのです。
🌸まとめ:戦わない将軍が見つけた「平和」
かつて日本の命運を担った徳川慶喜。
しかしその晩年は、権力から最も遠い場所――家族と自然、そして趣味に囲まれた静かな世界にありました。
釣り糸を垂れ、カメラのレンズを覗き、時代の変化をただ穏やかに受け止める。
その姿は、どんな勝者よりも満ち足りていたのかもしれません。
“将軍から趣味人へ”――
徳川慶喜の生涯は、
「権力よりも自由を愛した日本人」の象徴そのものでした。
まとめ
徳川慶喜という人物は、歴史の中でしばしば“裏切り者”“逃げた将軍”と語られてきました。
しかしその実像は、まったく異なるものでした。
大政奉還によって血を流さずに時代を変えた冷静な政治家。
自らカメラを操り、風景を写し取った先進的な芸術家。
自転車で風を切り、釣り糸を垂らして静かな時間を楽しむ趣味人。
彼は、武士の時代と近代日本の狭間で、誰よりも早く「次の時代」を生きた男でした。
剣を手放し、レンズとハンドルを握り、権力よりも“生きる喜び”を選んだ。
その姿は、変化を恐れず、人生を味わい尽くした知的な紳士のようです。
“最後の将軍”でありながら、“最初の近代人”。
徳川慶喜は、日本が新しい時代へ歩み出す瞬間に、
静かにその扉を開けた——そんな存在だったのではないでしょうか。
■MISSION JAPAN|クーリング系アパレル商品
MISSIONは、独自の「HydroActive™(ハイドロアクティブ)」冷却技術を搭載したゲイター、帽子、タオル、シャツなどの製品を提供しています。

■GALAPAGOS |メンズ向けバッグ
おもにメンズ向けのバッグを取り扱っております。
メイン商品は、ダッフルバッグ、バックパック、ショルダーバッグ、クロスボデイバッグなどです。

■馬刺しの極み|初回限定!極み馬刺し3種お試しセット(3900円~)
「馬刺しの極み」では、熊本産の厳選された本格馬刺しをお届けしています。