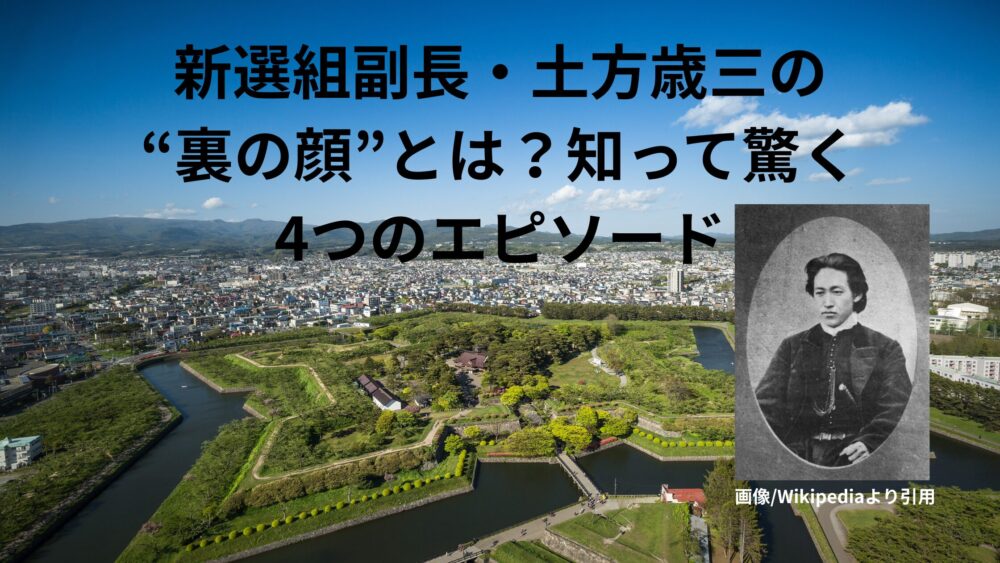【有名な話】函館戦争での壮絶な最期|五稜郭で戦死した“最後のサムライ”
戊辰戦争の最終局面である函館戦争において、土方歳三は旧幕府軍の一員として徹底抗戦を続けました。彼は榎本武揚らと共に北海道へ渡り、箱館の五稜郭に拠点を置いて新政府軍に対抗。自ら騎兵隊を率い、連日最前線に立ち続けました。そして1869年5月11日、一本木関門付近で銃弾を受け、壮絶な戦死を遂げました。このとき彼は35歳。最期まで「武士の美学」を貫いたその姿は、今なお“最後のサムライ”として多くの人の心に残っています。彼の死後、五稜郭も陥落し、幕末の一時代が完全に終わりを迎えました。
実は“和漢薬”の行商人だった?
土方歳三といえば、新選組の副長として幕末を駆け抜けた剛毅な武士というイメージが強いですが、彼の青年時代はまったく異なるものでした。実は歳三は農家の生まれで、正式な武士階級ではなく、身分的には「農工商」の中間層に位置する一介の町人でした。
そんな彼が若いころに生業としていたのが、「石田散薬(いしださんやく)」という和漢薬の行商です。この薬は、打撲や捻挫、筋肉痛などに効果があるとされ、地元・武州多摩地方ではよく知られた民間薬でした。彼はこの薬を背負って、徒歩や馬で村々を巡りながら販売していたとされます。しかも、ただ売るだけでなく、接客、勘定、配達、時には剣術修行を兼ねて道場に立ち寄るなど、多面的な経験を積んでいたようです。
この行商時代の経験が、後の歳三に大きな影響を与えたと考えられています。たとえば、
- 客との対話で鍛えた観察力や説得力
- 野外での長旅を通じて培った体力と忍耐力
- 商品や金銭を正確に扱う几帳面な性格
これらは後の新選組での規律統制や戦術判断にも活かされたといわれています。
また、歳三はこの頃から身だしなみにも気を使っていたようで、整った髪形や清潔な服装を保つ几帳面さも、この行商人時代からの名残だという説もあります。
彼がのちに「鬼の副長」と恐れられるほどの鉄の規律を持ち、また戦場でも冷静沈着でいられたのは、こうした“地に足の着いた商人経験”に裏打ちされた現実感覚や人間力によるものだったのかもしれません。
■当社グループ独占の人気商品!【家庭用ルームランナー販売店】
アジアNo.1メーカーであるジョンソンヘルステック社製、 その中で当社グループでしか取り扱いの無いルームランナーが、 「シリウストレッド8」です。
「俳句」が得意で“雅号”を持っていた?
「鬼の副長」と恐れられた土方歳三には、実は繊細な感性を持つ“文人”の顔もありました。その象徴とも言えるのが、彼が俳句をたしなみ、“豊玉(ほうぎょく)”という雅号(がごう)を使っていたことです。
この「豊玉」は、歳三が自ら名乗った号であり、武士でありながら文学的な趣味を持っていたことを示す貴重な証拠とされています。彼の句は現存数こそ少ないものの、その一部は現在も記録に残されており、風情ある表現が垣間見えます。
たとえば代表的な一句が以下のものです。
鉢叩く 音の寒さや 冬の月
(はちたたく おとのさむさや ふゆのつき)
この句は、鉢叩き(仏教的な修行や托鉢を連想させる音)が冬の寒さを際立たせる、という情景を詠んでいます。新選組として緊迫した日々を送るなかで、このような静寂や自然との対話を詠んだ句を残しているのは、土方の内面に深い情緒や観察眼があったことを示しています。
さらに、当時の俳句や和歌は、教養ある者の嗜みとされ、句会などで交流を持つ場でもありました。土方もそうした文化人との接点を通じて、戦乱の時代においても精神的な安らぎや自己表現を求めていたと考えられます。
また、土方の字(あざな)である「義豊(よしとよ)」の「豊」と、雅号「豊玉」の「豊」が重なることから、自らの名前への愛着や美意識も表現していたのかもしれません。
「非情の剣客」としての顔とは裏腹に、四季を感じ、静寂を愛し、言葉に思いを託す感性豊かな一面。それが「豊玉」としての土方歳三の姿だったのです。
戦の最中に“敵将に礼状”⁉土方歳三の武士道
土方歳三の人生には多くの戦いがありましたが、彼が単なる剛腕の戦士ではなく、礼節と義理を重んじる人物であったことを示す逸話として語り継がれているのが、「敵将への礼状」のエピソードです。
これは、戊辰戦争の最中、敵軍である官軍(新政府軍)の指揮官に対して、土方が感謝と敬意を示す手紙を送ったとされる話です。具体的には、戦闘で負傷した新選組隊士たちが捕虜となった際、敵軍が彼らを丁重に介抱し、粗末に扱わなかったことに対して、土方がその行為に感銘を受け、正式に礼状を送ったという内容です。
このエピソードが特筆すべきなのは、「戦争中であっても義を尽くす行為」に対して「義をもって報いる」という徹底した武士道の精神を土方が実践していた点にあります。
当時、敵味方の境界は厳格で、裏切りや残虐な処刑が珍しくなかった時代において、敵軍に対して礼節を尽くすという行動は極めて異例でした。そのため、この行動は土方歳三という人物の冷静さ・人間的な器・戦場での高い倫理観を物語るものとして高く評価されています。
この礼状の真偽は、一部では創作説や伝聞とされることもありますが、それでもこの逸話が長く語り継がれてきたのは、土方が単なる“鬼の副長”ではなく、義を重んじ、敵にも敬意を払える理知的な戦士だったというイメージを象徴するからに他なりません。
なお、同様の“敵に礼を尽くした逸話”は西郷隆盛や山岡鉄舟にも見られ、幕末の英雄たちが共通して持っていた「戦っても、人としての道は外さない」という思想を、土方も体現していたことがわかります。
まさに、刀で戦いながらも心に礼儀と誠を失わなかった“最後の武士”──それが土方歳三の真の姿なのです。
■人間の耳と同じ働きをする立体集音器【みみ太郎】
「人工耳介」による集音技術を開発。(特許技術です) この人工耳介にマイクを着けることで立体的に集音し、自然な聞こえを実現することに成功!
最期まで「剃刀と整髪料」を手放さなかった?
新選組副長・土方歳三といえば、冷徹な軍律、鋭い眼差し、そして凛とした姿勢で知られる「鬼の副長」。そんな彼が、戦場においても「身だしなみ」に細心の注意を払っていたという逸話は、彼の人物像に深みを与える興味深いエピソードです。
特に注目されているのが、最期の戦いとなった箱館戦争(戊辰戦争末期)においても、土方が“剃刀”と“鬢付け油(びんつけあぶら)”を携帯していたという記録です。これは、戦地の生活がどれほど苛酷であろうとも、常に髪型を整え、清潔感を保つことにこだわっていたことを意味します。
鬢付け油は、当時の髷(まげ)や髪型を整えるために欠かせない整髪料で、武士や力士などが使っていたもの。剃刀は髪の生え際や髭を手入れするために使用されていました。これらの道具を戦乱の真っただ中にも手放さなかったというのは、土方の“美意識”と“武士の矜持”を象徴するエピソードです。
この几帳面さは、新選組時代からすでに知られており、隊士の服装や髪型、礼儀作法にも厳しく指導していた背景があります。乱れた身なりは心の乱れを表すとして、武士である以上、外見もまた“戦う姿勢”の一部と考えていたのでしょう。
箱館戦争の最中、仲間が次々に倒れていく中で、土方はあくまでも冷静沈着で、そして端正な姿を崩さずに戦い続けました。その姿に、味方だけでなく敵軍の中にも感嘆の声を漏らす者がいたとも伝わります。
剣の腕だけでなく、精神のあり方、そして見た目の整え方にまで気を抜かない。最期の時まで“武士”であり続けた土方歳三の強さと美しさが、この剃刀と整髪料という小道具に凝縮されているのです。
まとめ
「鬼の副長」として知られる土方歳三は、確かに冷徹な規律と戦術眼を備えた武闘派の印象が強い人物です。しかし、その裏には、若き日には和漢薬を背負って行商をしていた庶民的な過去や、俳句を嗜み「豊玉」と名乗った文人としての一面、さらには戦場で敵将に礼状を送るほどの礼節を重んじる武士道精神、そして最期まで剃刀と整髪料を手放さなかった美意識と几帳面さがありました。
これらの逸話は、土方が単なる剣の達人でも、冷酷な軍人でもなく、人間としての深みと品格を持ち合わせた人物であったことを物語っています。剣と句、理と情、強さと美しさ──そのすべてを兼ね備えていた土方歳三だからこそ、今なお多くの人々を惹きつけるのでしょう。
■ナイツが絶賛!超心地よいヒンヤリ安眠枕【六角脳枕】
めざましテレビをはじめ各メディアで話題騒然!人気芸人ナイツも絶賛! 楽天「低反発枕」ランキングでも連続1位。
■医療従事者が推奨するNMNサプリ No.1【GAAH】
NMNサプリ分野において『医療従事者が推奨するNMNサプリ No.1』を獲得し、 GaahのNMNサプリメントを専門分野の違う5名の医師が実際に使い続けたいと回答。
■腰痛でお悩みの方へ★高い体圧分散性と雲の上の寝心地【雲のやすらぎプレミアム】
大人気シリーズの「雲のやすらぎプレミアム」マットレスがさらにパワーアップしてリニューアル! 雲のやすらぎプレミアム マットレスIIは、「眠る喜びを再発見できる」そんなマットレスを作りました。
■グリーンラビット
可愛らしいうさぎやネコのデザインが施されたアパレルコレクション。メンズ・レディースともに楽しめる、シンプルながらも遊び心のあるデザインが魅力です。カジュアルなTシャツやスウェットから、上品なシャツやジャケットまで幅広く展開。